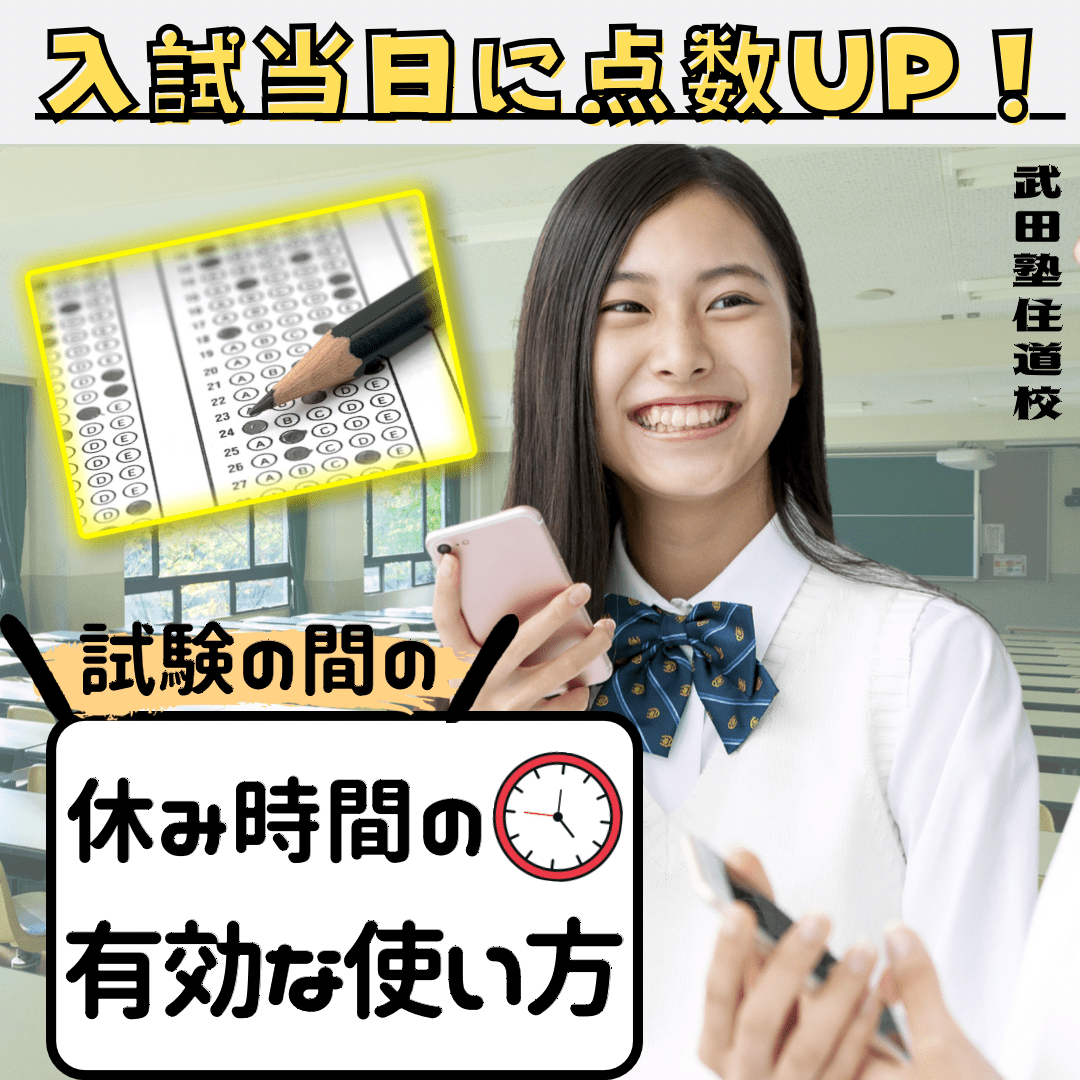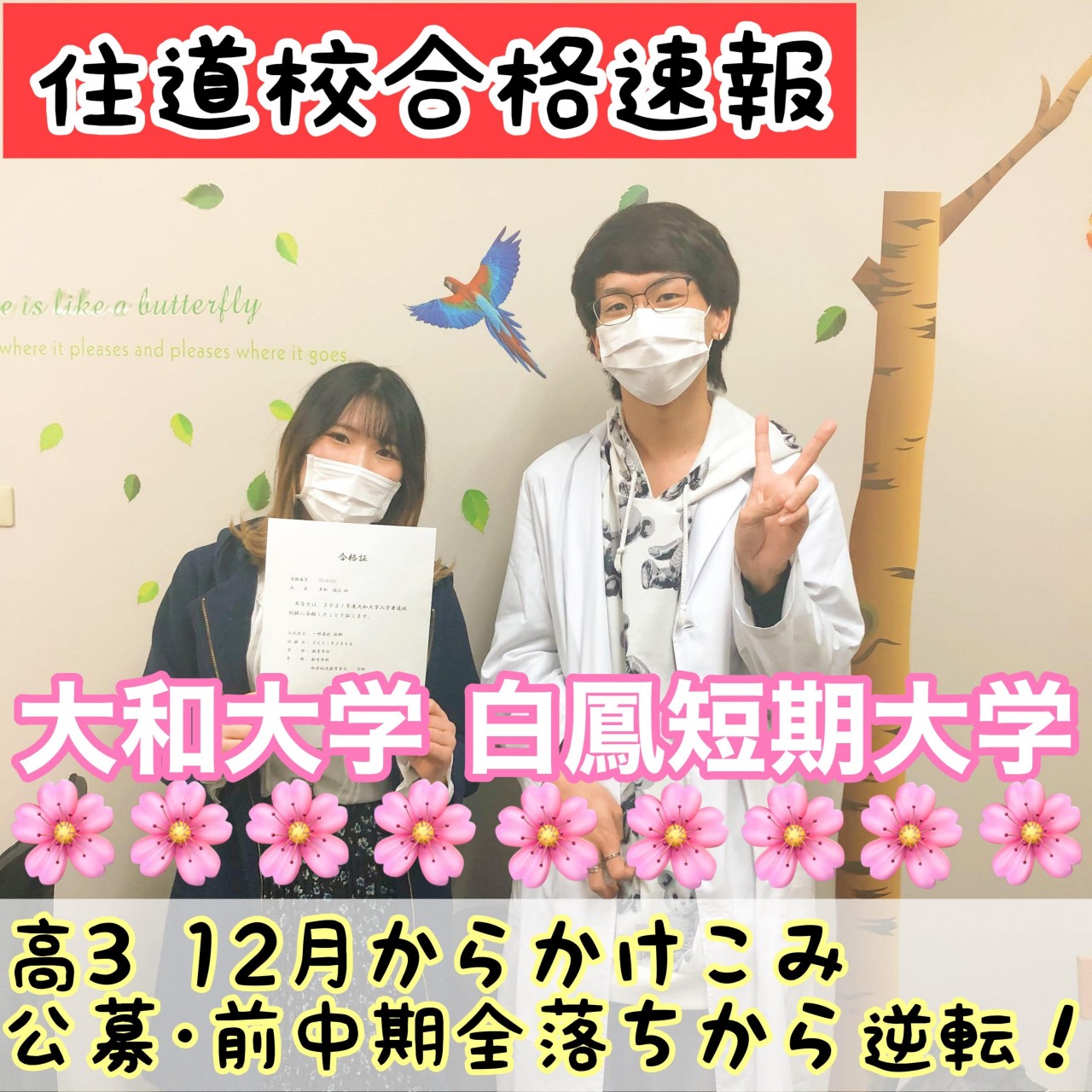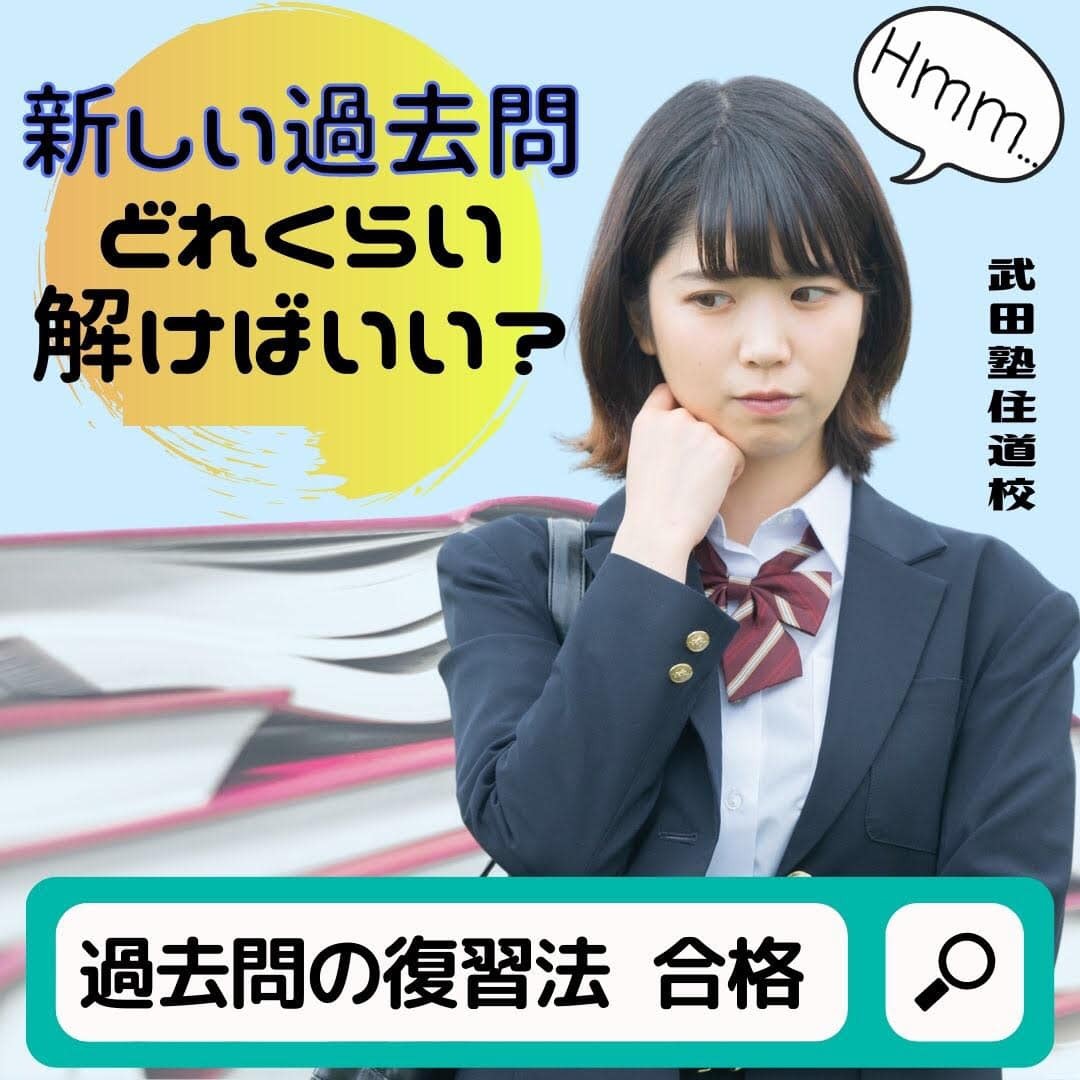
こんにちは!武田塾住道校です。
武田塾住道校では、普段から生徒の受験に対する悩みなどの相談に乗っているのですが、
入試直前期の本日あった質問を取り上げたいと思います。
今日は共通テストや私立一般入試直前期の今、この時期起こりがちな疑問
「今から新しい過去問を解くべきですか?」
について話していきたいと思います。
あなたがもし現在、過去問をどんどん解いている時期なら、
合計何年分くらい解けばいいのか、悩むことも多いと思います。
まだ過去問を始めていない人でも、
どれくらい解けば十分なのか、不安になると思います。
今回は、そんな疑問に終止符を打つべく、
武田塾住道校の校舎長松本が、まさに今日塾生にしたアドバイスを
記事を読んでくれているあなたにも紹介します!
また、新しい過去問をどれくらい解くのか、に大きく関わる
「過去問の復習法」もバッチリ紹介します!
過去問に関してはこちらの記事!という言えるくらい
ボリューム満点でいきますので、ぜひ最後まで読んでください!
入試直前期!入試直前に「新しい過去問解く」基準とは?
直前期は過去問演習が大事、なのは当然ですが、
試験まであと一週間を切ってくると、
「今まで解いた過去問を解くべきか」
「直前でも新しい過去問を解くべきか」
悩む人も多いんじゃないでしょうか?
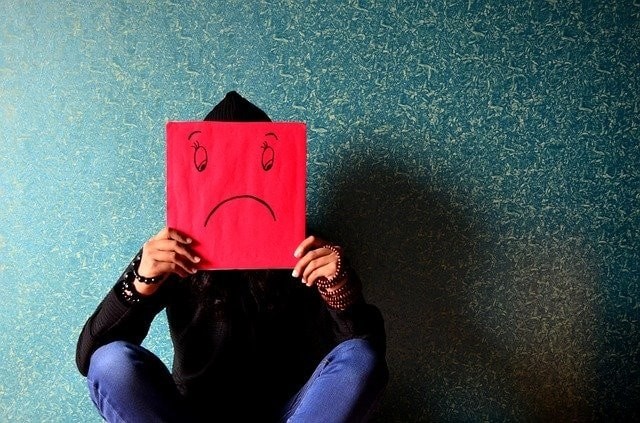
まず結論から言います!
この時期に新しい過去問を解くかどうかの基準は
「”完璧にできる”ようになるまで復習ができるか」です!
この時期の正しい過去問の復習とは?
まず、この時期に必要な過去問の復習の考え方を紹介したいと思います。
過去問演習の目的
初めに、過去問演習の目的をはっきりさせておきましょう。
それは、
「合格点をとれる力をつけること」です!
こう言うと、当たり前のように聞こえるかもしれません。
しかし、意外と、本当に「力のつく」復習を出来ている人は少ないと思います。
過去問を解いて、採点をし、見直しをする。
ここで終わっている人も多いんじゃないでしょうか?
しっかりと過去問を使えている人は
その後に解き直しまでできている人もいるかもしれません。
しかし、それでも不十分です!
これでは、過去問のその問題が解けるようになっただけで、
本当に「次解く過去問で点数が取れる力」がついたことにはなりません。
過去問の正しい復習方法①暗記系科目
では、ここから、科目・単元の性質別に正しい復習方法を見ていきます。
まず、化学・生物・地学の一部の単元や、社会科目、また、英文法問題など
暗記系科目の復習方法についてです。

ここでの目標は、
「出来ていない単元に関する内容を全て参考書などで完璧にする」ことです。
過去問を解いて、得点を出したら、
その中で最も得点の低い単元を洗い出します。
理科や社会に関しては、最も得点の低い大問
英文法に関しては、その問題でポイントとなる文法事項
が何か、を確認します。
自分でわからなければ、赤本の出題単元一覧で確認する事もできます。
それが分かれば、あとは、自分の使っている講義系の参考書の出番です!
その範囲を完璧にしにいきます。
ここで注意なのが、間違えた問題の範囲、ではなく
「間違えた問題を含む単元全て、を完璧にしなければならない」
という点です。
いまその問題を間違えたということは、
その単元そのものが完璧になっていない証拠です!
違った角度からの問題が出れば、また点数を落とす可能性が大きいです。
かならず、平衡なら平衡、代謝なら代謝、仮定法なら仮定法、と
その範囲全てを潰しにかかってください!
完璧になったら、最後はその過去問に戻って、
解けるか確認したら一単元完了です!
余裕があれば、違う年度の過去問でその単元の問題のみ演習してもOKです。
これを時間の余裕に応じて、1~2単元分やって、次の過去問へ、という感じです。
過去問の正しい復習方法②演習系科目
次は、数学、物理などの計算演習などの必要な科目についてです。
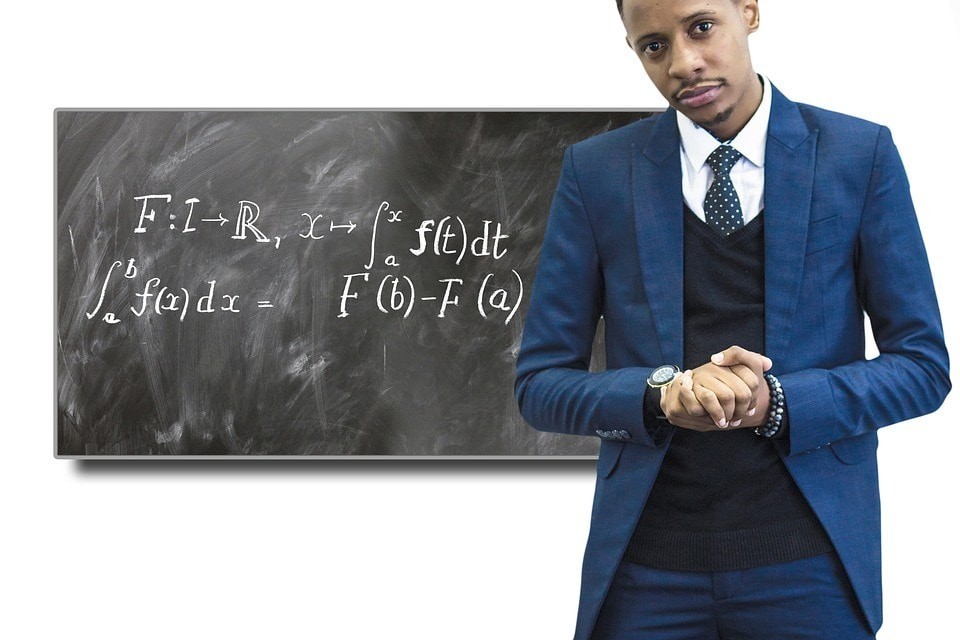
基本的には、①の暗記系科目と同じで、
「その単元の類題を参考書で解けるようにする」のが目標です。
そのとき、暗記系科目のときより意識してほしいことがあります。
それは、「その解き方をする理由が分かっているかどうか」です!
その公式や、その解き始めの式変形、その前提条件で
「問題を解き始めることができるのはなぜか?」
「どこを見ればよいのか?」
を必ず理解するようにしてください!
それを意識できると、
参考書で解き直さなければならない問題のパターンも一目瞭然となります。
過去問の正しい復習方法③読解系科目
最後に一番悩みがちな、国語や英語長文といった読解系科目についてです。
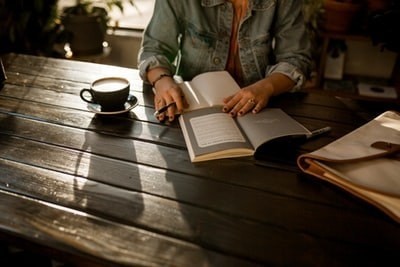
これについては、復習の考え方が2通りにわかれます。
1.インプットに抜け漏れが見つかったとき
2.問題の解き方が不十分だったとき
の2通りです。
1.インプットの抜け漏れの復習法
まず、1の場合は簡単です。
英文法や、単語、漢文の句法、現代文の語句など
インプットが足りていないことが原因の場合、
復習方法の①で挙げた、「その単元全てを完璧にする」方法でOKです。
2.問題の解き方の復習法
では悩むのが2です。
「本文の意味はだいたい理解できたのに解けなかった」
というのがこの時期よくある悩みではないでしょうか。
こんなときは、
「その問題を解くために使った考え方」に注目します。
「どこをみればよかったのか?」
「なぜ本文のその場所を見れば答えの根拠がある、とわかったのか?」
「本文をどのように読めば、そのような要約が出来たのか?」
をしっかり確認する必要があります。
それが分からなければ、読解の講義系参考書に戻ることも必要でしょう。
『きめる!センター現代文』や『田村のやさしく語る現代文』などがその一例です。
上記のようなことをクリア出来たら、
もう一度その問題に戻り、きっちり根拠がとれるようであれば完了です。
要するに、読解系のインプットに問題が無い場合は
「読み方、解き方」を理解できるようになる、というのが目標になります。
過去問の使い方については、以下の動画も参考にしてみてください!
「新しい過去問か」「今までの過去問の見直しか」の基準
では長くなりましたが、本題です。
新しい過去問に取り組む基準、覚えてますか?
「”完璧にできる”ようになるまで復習ができるか」でしたよね。
ここまで聞けば、少し具体的に分かったのではないでしょうか。
上記で上げた復習が、きっちり消化できる時間があるなら、
次の新しい過去問に取り組む意味はあります!
しかし、それが不十分になるくらいなら、
今まで解いた過去問で上記のことがきちんとできているか
確認する方が得点に繋がります!
具体的には、
「もう明日が共通テスト本番で復習の時間は無いけど、共通テストの問題を解きたい!」や
「直前に新しいものを解いて不安な気持ちになりたくない!」という場合は、
今まで解いた過去問を、
暗記系なら、きっちり完璧なまま覚えられているか
演習系なら、解く過程が問題文だけでイメージできるか
読解系なら、正しく文章を整理して読み、解答根拠がわかるか
を意識して、もう一度解きましょう!
上記のことをしっかり意識すれば、
2度目の過去問で、直前に身につけたい力がきっちり身につきます!
過去問の使い方 まとめ
長くなりましたが、いかがだったでしょうか?
過去問の復習方法、また、新しい過去問を解く基準
少しでもわかっていただけたでしょうか?

まとめると、
「”完璧にできる”ようになるまで復習ができるか」
を考えて、それが出来る時間の余裕があるなら、
迷わず新しい過去問に進み、得点力アップを目指しましょう!
それが時間的に出来ない、または
直前に新しい問題を解くと不安になる、という場合は
一度解いた過去問で、問題に必要な知識や考え方が
「完璧に」なっているか、を確認しましょう!
皆さんの不安が少しでも解消できていればうれしいです。
あと一息、最後まで頑張っていい結果を出してください!
武田塾住道校では、生徒の不安や疑問をそのままにはしません!
今回の質問のように、武田塾住道校では、
生徒の日々の不安や疑問はすぐに解消し、
すっきりした気持ちで勉強に臨めるよう、生徒たちにアドバイスを行っています!
また、過去問に対する課題分析も、
すぐに自分で的確に行うのはそう簡単ではありませんので、
自分でできるようになるまで横について分析のサポートを行います!
塾生だけではなく、無料受験相談では、誰でもアドバイスを受けることができます!
一生懸命勉強していても、自分だけでは解決しない問題が山ほどあります...
少しでも何か、勉強について不安や悩みがある方は、
今すぐ、武田塾住道校へ足を運んでください!
校舎長の松本が徹底的にカウンセリングを行います!
無料受験相談で、進むべき方法を一緒に決定しましょう!
👇ご予約優先とさせていただいておりますのでこちらからどうぞ!
お会いしてお話しできるのを楽しみにしています!