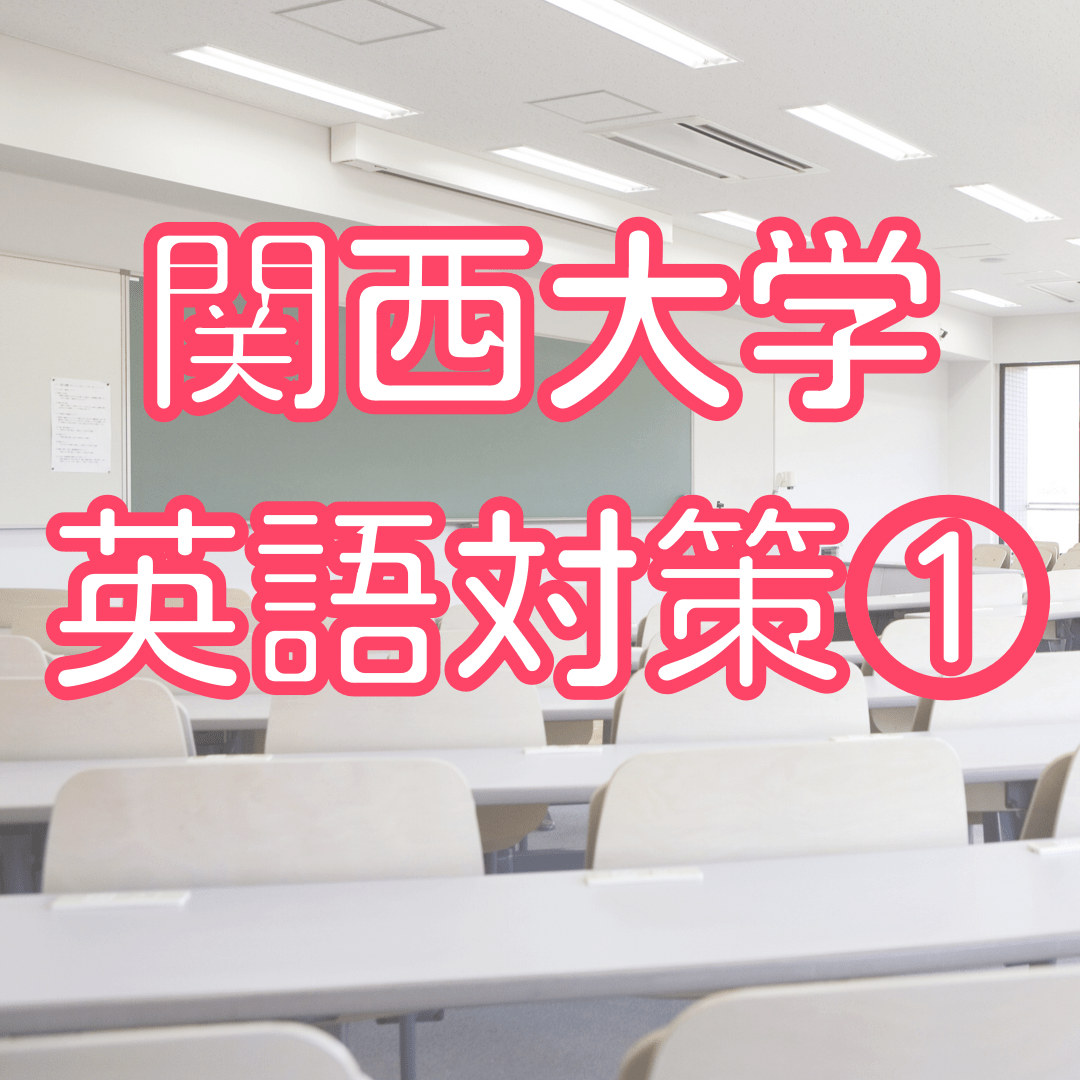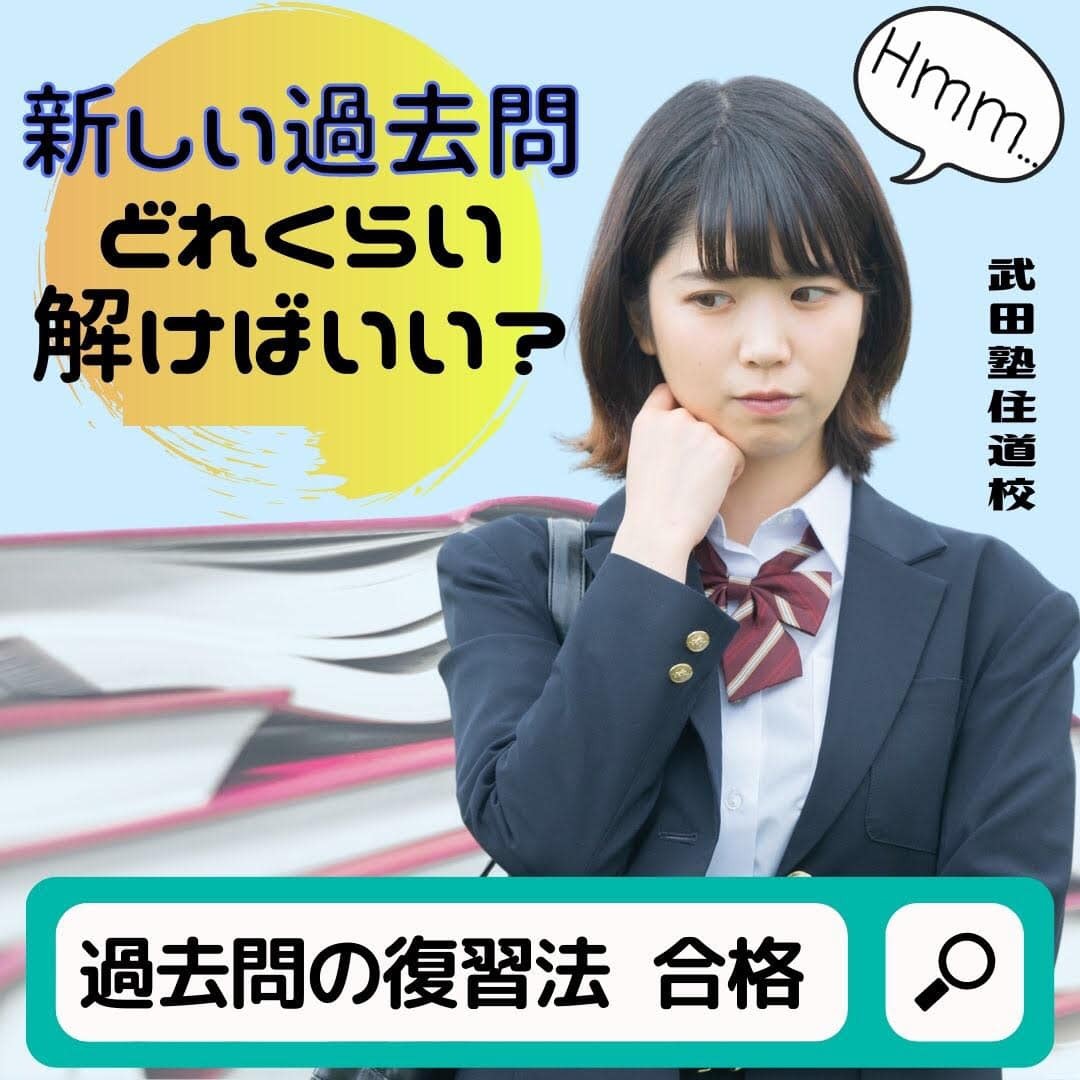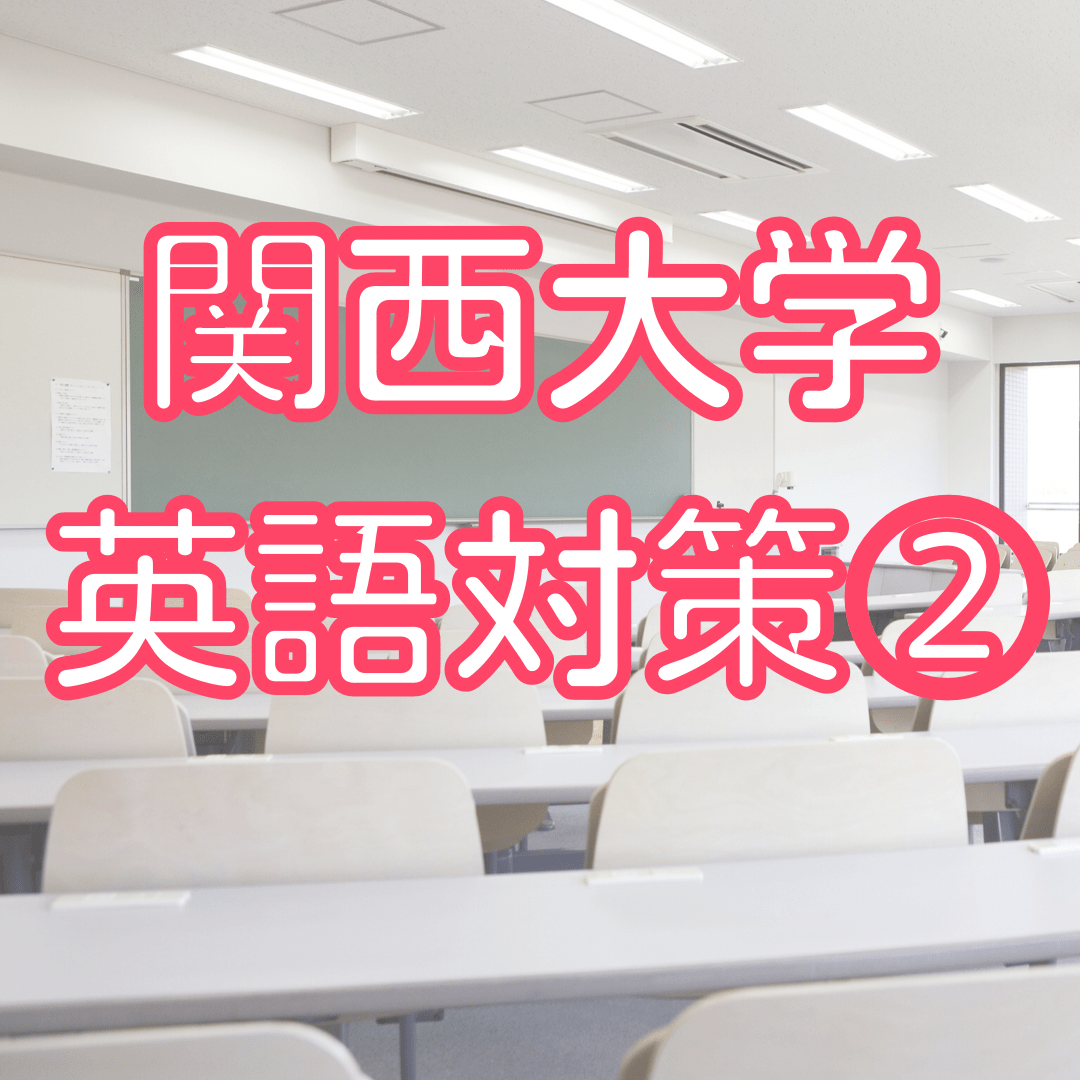
こんにちは、逆転合格の武田塾住道校、松本です。
センター試験も終わり、私立一般入試も続々と始まります。
合格最低点と、自分の現在の得点を比べて焦っている受験生も多いと思います。
そこで、今回は、
「直前でも点数が上がる関大英語の勉強法」
について紹介します。
前回記事では、関大英語でマストで得点しておきたい第1問ABについて、
解き方や必要な対策を紹介しました。
今回は、メインとなる第2問・第3問の長文読解問題について話します。
直前でもまだやれる!?関西大学の英語で合格点をとる方法とは?Part.2
まず、全体像を振り返ります。
関西大学の英語はどの日程も同じ問題形式です。
解答はすべてマーク式です。
まず関西大学の英語は全体として、
会話文・段落整序問題が1題ずつ、長文読解問題が2題の構成。
試験時間は90分で、200点満点の試験となります。
合格のための目標点は、科目間のバランスにもよりますが、
160点は欲しいところです。
第2問 長文読解問題(配点88点)
第2問の長文読解問題は、Aの空所補充とBの内容説明問題です。
大問3のほうが得意な受験生が多く、特にAの空所補充に苦労する人が多いです。
ただ、逆を返せば、Bの内容説明問題は選択肢が3択で非常に解きやすくなっていて
Aの空所補充に惑わされてBの内容説明問題を失点するのは非常に痛いです。
さらに空所補充は、文脈判断や語彙の難易度によって
とらなくてよい問題もまれに出題されるため、
戦い方としては、まず難易度の低いBの内容説明問題を満点狙い、
Aを出来るところまで解答する、という形が理想的です。
目安の解答時間は約40分です。
第2問全体を通した解き方
まず、第2問全体の解き方の方針を紹介します。
解き方の型が定まっていない人は、すぐマネしてください!
①長文やAの問題よりも先にBの設問を見る!
事前のヒント情報があるだけで長文は非常に読みやすくなります。
Bの設問をみて、文章のテーマや概要、設問で聞かれるキーワードをチェックしましょう。
それだけでおおまかな長文内容がわかってしまいます。
選択肢はまだみなくて良いです。
②段落ごとに読み、解ける問題を解いていく!
戦い方、のところでもお話ししましたが、
関大英語の長文はBの問題をベースに解いていくことが合格のポイントです。
なので、段落ごとに内容を整理して読み、その都度Bの問題を解き進めましょう。
一気に読んでしまうのも、段落途中で「解ける」と思って読みとめてしまうのも
問題を解く上で、マイナスに作用することが多いです!
逆に言うと、段落をまたいで解かなければならない問題はほぼない、
と思ってもらって大丈夫です!
Aの空所補充については、ぶつかったときに解いても、
段落を読み終わった後に解いてもよいですが、
段落途中に解いてしまって段落内容を見失ったり、
逆に途中に( )があるから、内容が入ってこない、
ということにならないようにしましょう。
なにより、段落内容理解が大事!と心得てください。
第2問A 空所補充問題の解き方(配点60点)
空所補充問題は語彙と文脈で解く!
Aの空所補充問題は、基本的に語彙力が問われます。
文脈にあう意味を考え、選択肢から選ぶ、というのが基本の解き方となります。
しかし、解く際に、単語の語法や、熟語など
その単語の使われる形に関する知識が有効な場合もあります。
しっかり選択肢と( )の前後の単語や文の形をチェックして解きましょう!
またまれに文法知識で解ける難易度の低い問題もあるので、
選択肢に並んだ単語の違いを見極めて、
「何が問われているか」に注意し、文法で解けるものは確実に仕留めましょう。
空所補充問題で「何が問われているか」見極めるコツ
設問で問われている知識が何なのか、は解いた後の復習にも非常に有効ですので
ここで、一つの見方を紹介します。
関大の空所補充問題では、
大きく分けて、①語彙や語法など単語の知識が問われているもの、
②知っているであろう単語を文脈に合わせることが求められているもの、
③文法が問われているもの、 に分けられます。
頻度としては、ほとんどは①と②、まれに③という感じです。
見極める際は、基本的に選択肢の単語のちらばりで判断します。
①語彙や語法知識が問われている問題
以下のような選択肢が一例です。
A. discovery B. overview C. application D. rejection
A. grow B. think C. feel D. stop
これらの選択肢の特徴がわかるでしょうか?
まず一つ目が語彙が問われているもの、二つ目が語法知識が問われているものです。
どちらも、全ての選択肢の品詞が同じであることが共通点です。
語彙が問われるものは、基本的に名詞や形容詞・副詞など、
前後の形にあまり影響を与えない品詞が並び、受験生が少々意味に悩む単語が含まれます。
この種の問題は語彙力勝負になります。
逆に、語法の問われるものは主に動詞の選択肢が並び、
どれも受験生にとっては簡単に意味が分かる単語が並びます。
この種の問題の場合、選択肢だけでなく、特に( )の後ろの形に着目して解きます。
②知っている単語を文脈判断で埋める問題
A. larger B. cheaper C. more D. worse
①と似ていますが、同じ品詞が並び、かつ特に難解でない単語が並ぶ場合は、
問題の根拠が前後の文脈に大きく関係します。
このような場合は、( )の付近を精読し、読解力で解答しましょう。
③文法が問われている問題
A. how B. if C. but D. as
A. then B. was C. since D. became
ここで挙げた選択肢の特徴は見てのとおりです。
一つ一つの文法的役割が異なるため、
( )前後の形を見て、文法的な判断で解ける問題です。
年度、日程によっては1~2問このタイプの問題が混ざっていることがあります。
他の問題に流されて文脈で解こうとすると、足元をすくわれてしまうので注意です。
第2問B 内容説明問題の解き方(配点28点)
この問題に対しては、全体の解き方でも示したとおり、
先に設問を読み、段落ごとに解くようにしましょう。
まず解く際の目の動かし方の順序ですが、
①Bの設問文を全て見通して、文章の概要をつかむ
②(1)から順番により詳しく設問を読み、解答根拠を探すヒントを見つける
③本文を段落ごとに読み、内容を整理していく
④自分で答えを何となくイメージしてから選択肢を見る
という手順で目線を動かしましょう。
では、②について、どのような視点で設問の見ればよいかコツを紹介します。
It is difficult for us to properly understand the achievements of the Corps of Discovery because ____
このような設問文があった場合、
まず、問われているポイントを押さえます。
beceuseの後ろが聞かれてるから、とにかく「理由」を探す。
「何の理由?」⇒「私たちが理解するのが難しい理由」
「何を理解するのが難しい?」⇒「Corps of Discoveryの成果を」
のように段階を追って考えます。
ポイントは、まず大まかに聞かれているのは、
「理由」なのか「場所」なのか「ある内容の要約」なのか「適切なタイトル」なのか
を判断します。
これを確認しておかないと
「本文には書いてあるけど、その設問の答えになっていない」という
的外れな選択肢にひっかかってしまいます。
それができたら、あとは、
本文から解答根拠を見つけるヒントのなるキーワードを拾います。
「Corps of Discoveryのachievementを理解するのがdifficultな理由」を聞かれているため、
上の で示した単語は本文中に出てくる可能性が高いです。
ここまで準備が整ったら、本文を段落ごとに読み、解答するだけです!
くれぐれも「見つけた!」と思って段落途中で答えないようにしましょう。
第3問 長文読解問題(配点68点)
第3問の長文問題は第2問の大問2の空所補充が下線部問題に変わっています。
Aが下線部の意味を問う問題、Bが第2問と同じ内容説明の問題です。
この大問では、第2問に比べて、より読解力が試される問題が多くなっています。
目安の解答時間は30〜35分程度。
第3問全体を通した解き方
大まかな解き方は第2問と全く同じ、
①長文やAの問題よりも先にBの設問を見る!
②段落ごとに読み、解ける問題を解いていく!
です。
しっかり意識して解いてください。
第3問A 下線部内容一致問題の解き方(配点40点)
下線部問題は語彙力で解ける問題も多少はありますが、
ほとんどが前後の文脈で判断する問題です。
ここでの注意点は、それっぽい選択肢に騙されないこと、です。
下線部だけを見て、照らし合わせると、なんとなくそれっぽいけど、
文脈的には絶対に合わない、ひっかけ選択肢が紛れている場合が多いです、
そこで、
選択肢を見ずに、先ず文脈から答えを考える
ことが攻略法です!
逆に言うと、大体の予想がついてないまま
選択肢に頼った解き方はかなり危険です!
これさえ意識すれば選択肢に騙されることが一気に減ります!
第3問B 内容説明問題の解き方(配点28点)
これは第2問Bと同様です。上記を参考にしてください。
関大英語の解き方 まとめ
以上のようなことを意識して、過去問演習してください。
満点をとるためには、意識だけでは不十分です!
過去問を解く中で、しっかり解き方を落とし込まないと、
常に安定して満点にはたどり着けません!
この記事を読んだ皆さんは、すぐに過去問の意識を変えてください!
第1問の対策について、まだ読んでいない人は一つ前の記事を見てください。
過去問演習の時間で損をしないように明確な対策をしましょう!
武田塾住道校の志望校対策
武田塾住道校では、以上のように、明確に傾向を分析した過去問対策を行います。
この様な意識付けで点数が上がるのは、基礎が固まっていることが前提です!
これから勉強を始める高1、2生
また、浪人を決めてより上を目指す高3生は
基礎の徹底に裏付けられた得点力を手にしてください!
武田塾住道校は目標を持った皆さんを待っています。
問い合わせなど詳しくは、記事の一番最後を見てください。
無料受験相談も受付中です!
武田塾住道校の無料受験相談が気になる人は、こちらもチェック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓