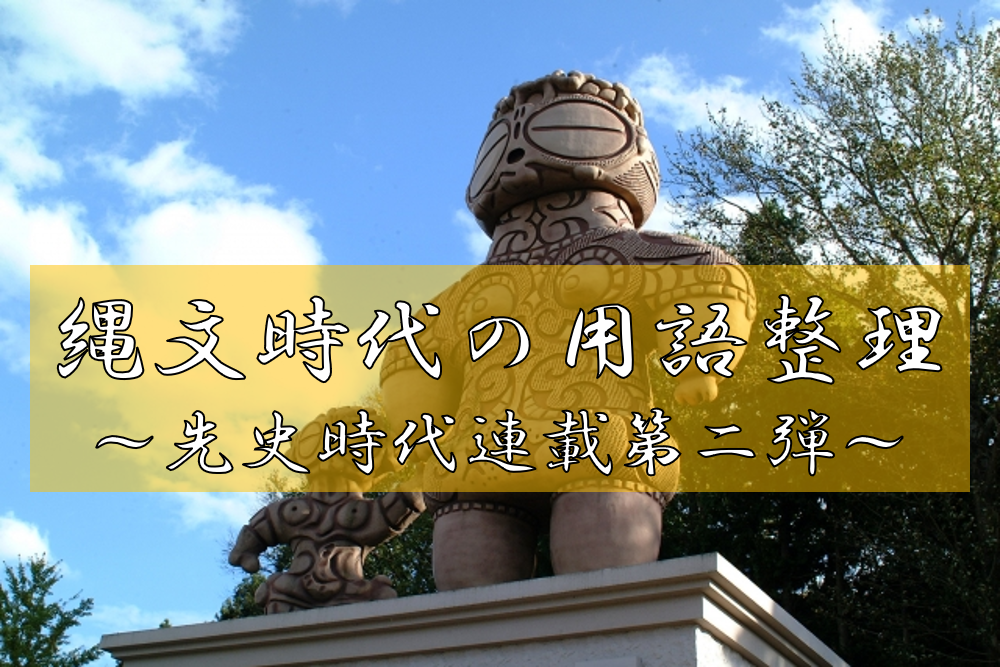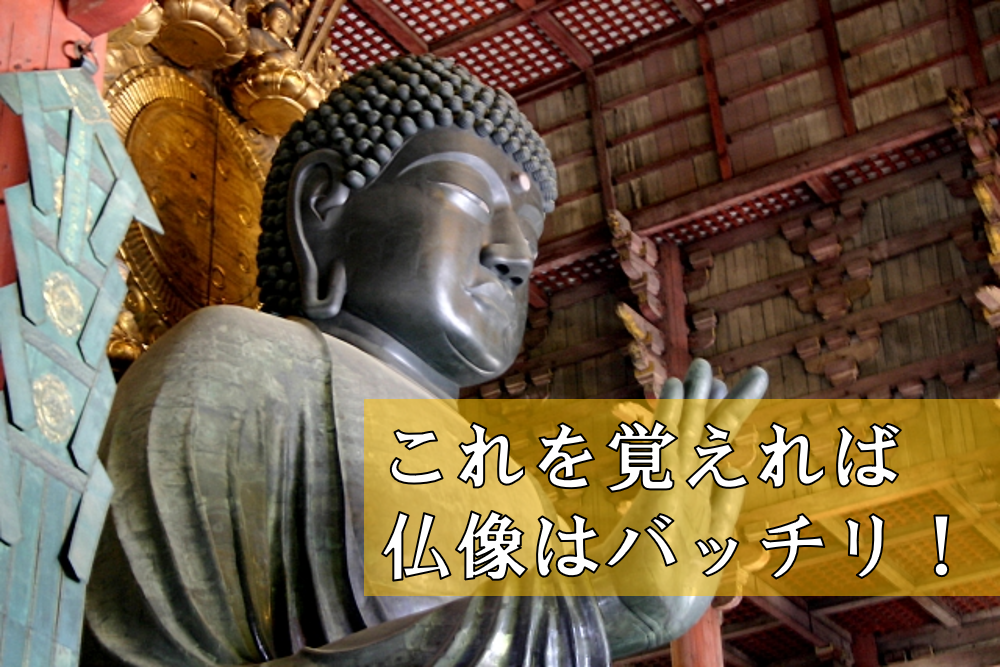こんにちは!京都駅の予備校・塾といえば、武田塾京都駅前校です。
今回は、日本史が大得意な講師に聞いてみた「先史時代連載」の第三弾!弥生時代についてまとめてもらいました(^^)/
先史時代連載第三弾 弥生時代
続きまして、第三弾、弥生時代です。
弥生時代は、日本史の教科書における3番目の時代に位置し、紀元前4世紀ごろから紀元後4世紀ごろに該当します。
この時代では既に中国や朝鮮半島の文字史料に日本列島の様子が記述されるケースもしばしばあり、そのような意味では「先史的」ではなく「歴史的」な時代ともいえますが、少なくとも日本において記述された歴史資料はないことから、先史時代の第三弾として紹介します。
中国や朝鮮半島の史料については別に勉強しておきましょう。
さて、この時代が前の縄文時代と区別されているポイントは、主に次のような点にあります。
・金属器の使用がはじまった。
・農耕、牧畜、機織りがはじまった。
・小国家の形成がみられる。
これらの新技術は多く朝鮮半島から移住してきた人々によって伝えられたと考えられており、弥生時代になって日本列島に移住してきたこれらの人々を、旧石器時代から日本列島に定着していた古モンゴロイドにたいして、「新モンゴロイド」といいます。
また、地理的観点からは次の点があります。
・九州から本州までしか弥生文化は広まらなかった。
すなわち、現在日本国を形成している部分で弥生文化を経験しなかった地域があるということです。
それゆえ沖縄と北海道で、これらの地域の先史時代における縄文時代以降の文化は、個別に暗記しておく必要があります。試験でもしばしば問われる事項ですので、把握しておきましょう。
以上の点に留意して以下の事項を整理していきます。
環境・生物
| 地理 | |
|
続縄文文化 |
紀元前後頃から8C頃まで農耕をせず狩猟採集を継続した北海道の文化 |
|
擦文文化 |
7~13C頃の北海道の狩猟採集文化。鉄器・擦文土器や北海道式古墳が特徴 |
|
オホーツク文化 |
9~13C頃の北海道オホーツク海沿岸の文化。独自の土器を使用 |
|
貝塚文化 |
弥生時代と同時期に沖縄で発展した貝の利用が特徴的な文化 |
|
人類 |
|
|
新モンゴロイド |
東アジアに分布する黄色人種のうち弥生以降北方から日本に渡来したもの |
前回の縄文時代では新たに磨製石器や土器、骨角器が出現しましたが、弥生時代には新たな土器である弥生土器や、青銅器や鉄器といった金属器が現れました。
したがって、どの道具がどのような形状で、どのような素材で、どのような場面で用いられたのかの区別は今までの時代より一層複雑になっており、それだけ出題のネタにされやすいということでもあるので、引き続き意識して覚えていきましょう。
全体としては、狩猟・漁労・採集が中心だった縄文時代と異なり、農耕、特に水稲耕作が普及した点が最も顕著な点です。
農耕が始まって余剰生産物の蓄積がおこると当然貧富の差が生じてきますが、そのような弥生時代においては縄文時代をはるかにしのぐ規模の建造物や集落が遺跡として残るようなりました。
したがって、このように人々の共同体が一層社会性を帯びてきた弥生時代では、農耕以外にも祭祀や戦闘の側面からも覚える必要のある事項が増えている点にも注意が必要です。
祭祀に関しては埋葬法や墓の多様化や金属製の祭器の製造が、戦闘に関しては集落の構造や武器が暗記事項のカテゴリーとして指摘できるところです。
先史時代には共通していえることですが、前回や前々回同様、遺跡は地図問題で出題されることもかなり多いといえます。
必ずどこにあるのか覚えられるよう、県名を付して記載しました。
旧石器時代や縄文時代の遺跡とも必ず区別しておきましょう。
余裕があれば地図上で場所を確認しつつ覚えると記憶にも定着しやすいでしょう。
社会・生活
| 社会:住居は竪穴住居。農耕は富の蓄積と格差を生み、小国家の形成や戦争も見られた | |
|
環濠集落 |
弥生時代を通じて見られた一般的集落。周囲を濠で囲っている |
|
高地性集落 |
弥生中後期の瀬戸内海沿岸に多い集落。軍事・防衛の都合による立地か |
|
高床倉庫 |
弥生時代から登場した建造物。収穫した作物を収納するための倉庫 |
|
水稲耕作 |
イネの栽培。縄文時代晩期に既に一部でみられていたが弥生時代本格化。 前期 湿田(湖沼を利用した水田)・石包丁で穂首刈り・直播 後期 乾田(灌漑設備を持つ水田)・鉄鎌で根刈り・直播(田植えも?) |
|
湿田 |
水田の種類。弥生時代前期に利用された。地下水位の高い沼沢地を利用したもの |
|
乾田 |
水田の種類。弥生時代後期に西日本を中心に利用された。灌漑設備を備えており、生産性が高かった |
|
穂首刈り |
イネの刈り方。弥生時代前期に実践された。石包丁で実の部分のみを刈り取るもの |
|
根刈り |
イネの刈り方。弥生時代後期に実践された。鉄鎌で茎の部分ごと刈り取るもの |
|
直播 |
イネの植え方。弥生時代を通して実践された。種もみを水田の地表にそのまま蒔くもの |
|
田植え |
イネの植え方。弥生時代に始まったとされる。発芽した苗を水田に植えるもの |
|
機織 |
弥生時代に日本に伝来した技術。紡錘車を用い草や木の皮で簡単な平織をした |
|
農耕儀礼 |
弥生時代に起こった農耕と関係する諸現象への信仰。 その様子は銅鐸の文様にも描かれた。後の祈年祭や新嘗祭の起源となる |
|
伸展葬 |
死者の両足を曲げない埋葬法。弥生時代に増加した |
|
支石墓 |
自然石の支柱の上に大きな平石を載せた墓。九州北部に多い |
|
甕棺墓 |
閉じられた土器の棺の中に埋葬する墓 |
|
箱式石棺墓 |
板石を組み合わせた箱状の墓。西日本に多い |
|
方形周溝墓 |
弥生前期から現れた四角形の低い墳丘を溝で囲う墓。家族墓らしい |
|
墳丘墓 |
弥生中期から現れた墓域を高く盛り土する墓。有力者の墓か。西日本に多い |
|
道具:農耕・祭祀・戦闘に使うものが目立つ |
|
|
弥生土器 |
薄手・赤褐色が特徴の土器類。縄文土器に比べ実用性が高く、文様も無文か簡素である。 農耕文化の影響をうけ、食に関係するものが多い |
|
高坏 |
土器。食事を盛る脚付きのもの |
|
甕 |
土器。食料などを煮沸するためのもの |
|
壺 |
土器。食料などを貯蔵するためのもの |
|
甑 |
土器。米を蒸すために底面に穴を開けてあるもの |
|
金属器 |
金属でつくられた製品類。弥生時代に製法が伝来した |
|
青銅器 |
銅と錫の合金で作った金属器類。鋭利さや強度で鉄器に劣り、その大半は祭祀用 |
|
平形銅剣 |
青銅器。瀬戸内海で多く作られた祭器 |
|
銅戈・銅矛 |
青銅器。九州で多く作られた祭器 |
|
銅鐸 |
青銅器。近畿で多く作られた日本独特の祭器。原始的絵画文様を持つものも |
|
銅鏡 |
青銅器。朝鮮や中国から輸入された祭器。権威のシンボルで、後期には一部で国産品も |
|
鉄器 |
鉄で作られた金属器類。鉄剣・鉄鏃のような武器以外はほとんど農具であった |
|
農具 |
農耕(特に水稲耕作)において用いられる製品類 |
|
木製農具 |
弥生時代を通じて利用された金属を用いない農具類 |
|
鉄製農具 |
弥生時代後期に普及した農具類。刃先の部分に鉄を取りつけたもの |
|
田下駄 |
木製農具。低湿地に入るとき足がめり込まないようにするもの |
|
大足 |
木製農具。田に肥料などを踏み込むためのもの |
|
木臼・竪杵 |
木製農具。収穫された穀物を脱穀するための木製農具 |
|
木鍬・鉄鍬 |
農具。振下ろして掘起こしたり、ならしたりするもの。後期には鉄製農具化したものも |
|
木鋤・鉄鋤 |
農具。足の力で土を掘起こすスコップ状のもの。後期には鉄製農具化したものも |
|
石包丁・鉄鎌 |
農具。穀物の収穫に利用するもの。前中期は前者(石器)、後期には後者(鉄製農具) |
|
紡錘車 |
機織に用いる道具。円盤形で棒を通す穴が開いている |
|
遺跡 |
|
|
青森県砂沢遺跡 |
弥生前期の遺跡。東日本最古ともいう水田跡が残る。青森県が弥生文化の北限 |
|
青森県垂柳遺跡 |
弥生中期の遺跡。水田と足形の跡が残る。青森県が弥生文化の北限 |
|
神奈川県大塚遺跡 |
弥生中期の遺跡。環濠集落であり、近辺には方形周溝墓群も |
|
香川県紫雲出山遺跡 |
弥生中期の遺跡。代表的な高地性集落の遺跡である |
|
佐賀県吉野ケ里遺跡 |
弥生時代を通じて栄えた遺跡。巨大な環濠集落であり、墳丘墓や物見櫓もある |
|
静岡県登呂遺跡 |
弥生後期の遺跡。高床倉庫や大量の木製農具が出土 |
|
奈良県唐子・鍵遺跡 |
弥生前~後期の遺跡。環濠集落であり、大量の弥生土器・木製農具が出土 |
|
島根県神庭荒神谷遺跡 |
弥生時代の遺跡。大量の銅剣、複数の銅矛・銅鐸が出土した。出雲王権の存在を示唆する |
|
島根県加茂岩倉遺跡 |
弥生時代の遺跡。大量の銅鐸が出土した。出雲の王権の存在を示唆する |
|
山口県土井ヶ浜遺跡 |
弥生時代の遺跡。海岸砂丘上の墳丘墓群。屈葬が多く、渡来人の系譜を示唆する |
|
岡山県楯築墳丘墓 |
弥生時代の遺跡。直系40mにも及ぶ巨大な墳丘墓である |
さいごに
弥生時代は以上となります。用語整理にぜひご活用下さい。
第四弾をお楽しみに~(^^)/
↓仏像史、建築史、清和源氏etc...日本史に用語整理に大活躍の記事をまとめました(^^)/↓
京都駅の予備校、京都駅の個別指導といえば!
大学受験の逆転合格専門塾【武田塾京都駅前校】
〒600-8233
京都府京都市下京区不動堂町482番地 YMビル3F
(JR京都駅・近鉄京都駅、徒歩7分!)
TEL:075-353-5333
武田塾では無料受験相談を実施中!
大学受験のお悩みを個別で伺い、一緒に解決していきます!無料受験相談は1人1人と丁寧にお話しさせていただくための完全予約制です。「一人で相談に行くのが不安…」という人は是非お友達・ご両親と一緒にお越しください(*’ω’*)
京都駅の予備校、京都駅の個別指導といえば!
大学受験の逆転合格専門塾【武田塾京都駅前校】
〒600-8233
京都府京都市下京区不動堂町482番地 YMビル3F
(JR京都駅・近鉄京都駅、徒歩9分!)
TEL:075-353-5333