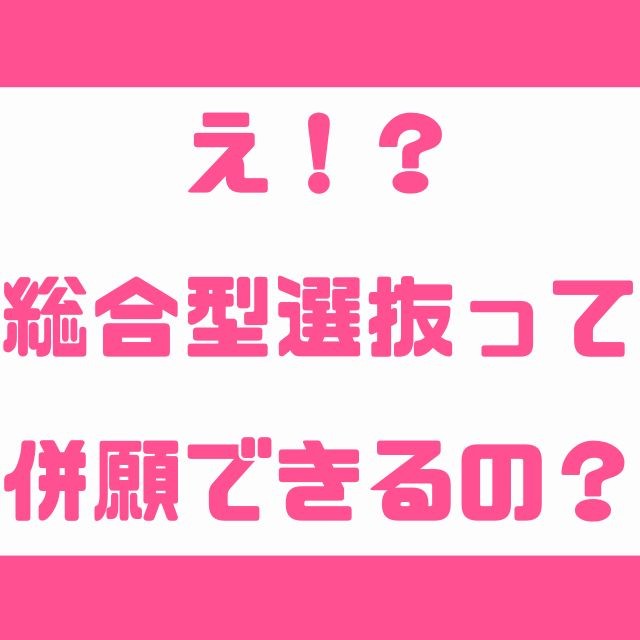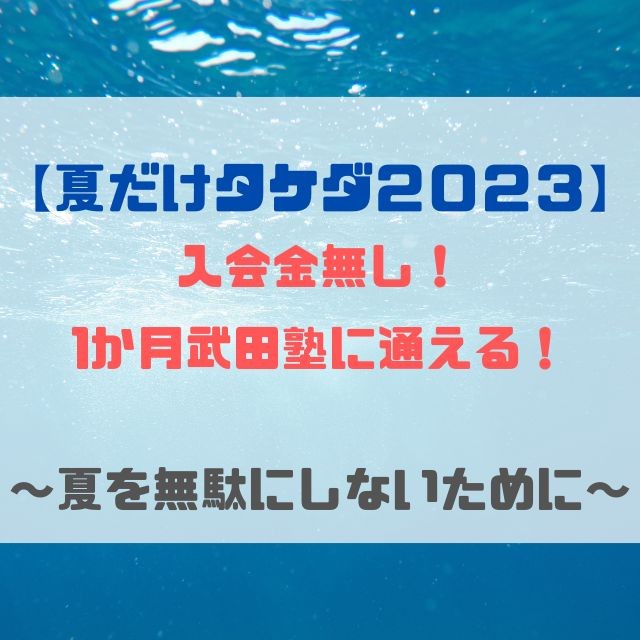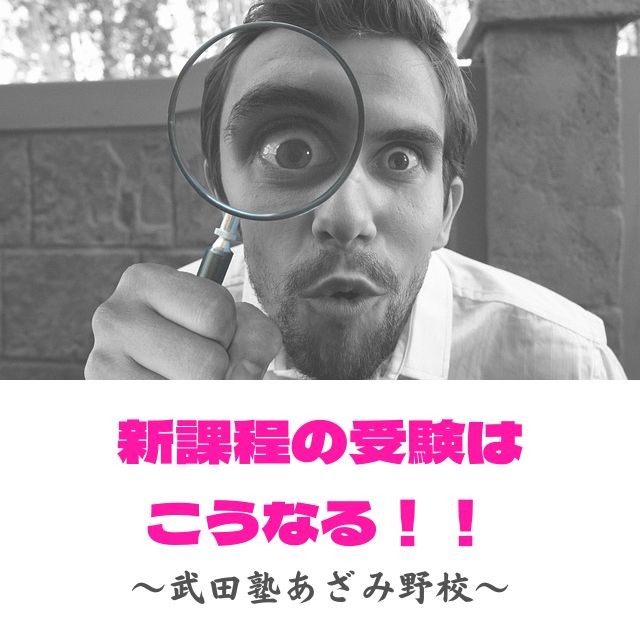
【高1,2年生は知っておくべき!】新課程の大学受験はこうなる!
皆さんこんにちは!
武田塾あざみ野校です!
今回は高校一年生、二年生向けのブログで、「2022年の高校一年生から適応される新学習指導要領で変容を遂げる受験の実態」についてお話していきます!
2021年に、大学入試センターから「平成30年告示高等学校学習指導要領に対応した 令和7年度大学入学共通テストからの出題教科・科目について 」が公表されました。
ここで大きな変更があったのは「数学」と「社会」で、「理科」等の他科目も教科の内容に一部変更が加えられました。
以下では「数学」と「社会」を中心に、現行課程との違いを解説しながら入試はどのように変わっていくのか、発表された情報をもとにご紹介していきます♪
1【新課程】数学
旧課程(現行の形式)では、
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B、数学活用が主な出題科目でしたが、
新課程では、
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B、数学Cとなりました。
新たに追加された数学C、これが最も大きな変更点です。
旧課程では数学ⅡBで学んでいた「ベクトル」や、数学Ⅲで学んでいた「数学的な表現の工夫」、「平面上の曲線と複素数平面」で構成されることになりました。
文系の国立受験生も数学Cのベクトルに関してはほぼ必須になり、
ⅠA+ⅡB+ベクトルといった表現もなされています。
他にも
数学ⅡBに「統計的な推測」が選択問題として導入された点や、整数が「数学と人間の活動」分野に取り込まれ重要性が低下された点等々、様々な変更点が加えられているので、一度ご自身の目で確認してください。
次に共通テストでの変更点をご紹介します。
まずはⅠAです。
発表された試作問題では、選択問題が消滅し「全問必答」となりました。
従来は、図形・整数・確率の3つの大問から2つを選択する形式でしたが、先に述べた整数の重要性の低下に伴い、「図形と性質」と「場合の数と確率」が必答になりました。
次にⅡBです。
共通テストの出題方式も
- 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」だった科目が「数学Ⅱ・B・C」という出題形式となり、
- 試験時間が60分から70分へと拡張されました。
発表された試作問題では、必答問題3題に加え、4題の中から3題を選択する形式となっています。
具体的には
【必答】
1数学Ⅰ
2図形の性質(数A)
3場合の数と確率(数A)
と
【選択】
1数列(数B)
2統計的な推測(数B)
3ベクトル(数C)
4平面上の曲線と複素数平面(数C)
の4題のうちから3題です。
文系の人も、理系の人も共にこの方式になった点は頭に入れておきましょう!
共通テストで「数学Ⅱ・B・C」を受験する場合は、「数C」の分野、すなわち「ベクトル」
か「複素数平面」の少なくとも1題は学習する必要が出てきたことに注意してください!
文系の人はⅡ以外から3題選択になるため負担が増しています!!
文系志望者の王道な選択は「数列」「ベクトル」+「統計的な推測」の3題
理系志望者の王道な選択は「数列」「ベクトル」+「平面上の曲線と複素数平面」の3題
になると思われます。
文系受験生は変更が加えられた数学Cのベクトルの扱いや、新領域の「統計的な推測」に関して、理系受験生は新領域の「複素数平面」の対策に関しては特に注意して取り組んでくださいね♪
次に国公立二次試験対策に出る影響について説明します。
共通テストでは「整数の対策が不要」になったり、「統計的な推測がほぼ必須」になったりしましたが、実際にこれらの変更に伴う対策が志望校の2次試験で通用するのかは、高校1年生・2年生のうちから確認しておくといいでしょう!
既に数校の有力大学が発表した「これらの変更を受けて入試範囲に変更を加えるのか」をまとめた表があるので以下に貼っておきます、参考にしてみてください!
https://univ-journal.jp/wp-content/uploads/2022/10/221011_kanb_column_02.jpg.webp
https://univ-journal.jp/wp-content/uploads/2022/10/221011_kanb_column_02.jpg.webp
最後に武田塾ならではの、これらの入試改革に立ち向かうための参考書ルートを提案して数学は締めさていただきます!
ベクトルの扱いが複雑化したことで、新課程版の参考書を使った対策が難化しています。
武田塾では、これから勉強を始める高校1年生・2年生には
「入門問題精講」をオススメしています。
新課程版の「数学ⅡB入門問題精講」にはベクトルが内包されていません!
「数学Ⅲ・C」の方には収録されていますが、文系受験生がわざわざベクトル対策のために当本を購入するのはなんだかめんどくさい気がしますよね?(笑)
そのため
新課程の「入門問題精講」に追加して、「坂田アキラのベクトルが面白いほどわかる本」を購入する作戦や、旧課程の「入門問題精講」に追加して「大渕智勝の統計的な推測が面白いほどわかる本」を購入する作戦が有用だと言えます!
『不足している単元を、適宜それに特化した参考書を購入して学習を進めていく』ことが必要なんだ!と、ざっくり高校1年・2年のうちに理解しておくと、今後の受験にも役立ちますよ!!
2【新課程】社会
なんと社会は【名称ごと変更】がなされます!!
旧課程では、
「地理A・B」
「日本史A・B」
「世界史A・B」
「現代社会」
「倫理」
「政治経済」
「倫理・政治・経済」
だった履修科目が、
新課程では、
「地理総合、地理探求」(旧地理A、地理B)
「歴史総合、日本史探求」(旧日本史A、日本史B)
「歴史総合、世界史探求」(旧世界史B、世界史B)
「公共・倫理」(旧現代社会)
「公共、政治経済」(旧政治経済)
「地理総合、歴史総合、公共(から2分野選択)」
へと大幅な名称変更が加えられています。
まずは「科目名」と「学習内容」を混同しないように注意してください!!
歴史系の科目に関しては
「日本史探究」「世界史探究」それぞれが単独の出題科目となるのではなく、必履修科目「歴史総合(日・世複合的な科目)」と組み合わせた形となることに注意してください!
日本史と世界史の両方を学習する必要があります!(ただし、近現代のみ)
地理系の科目に関しては
地理Aが必修科目となり、「地理総合」に改名された点が大きな変更点です。
歴史に加え、いままでは選択制だった地理が必修になったことに注意してください!
公民系の科目に関しては
「現代社会」が廃止となり、「公共」が新設され、必修科目となりました。
しかし学習内容に大幅な変更はありません!!
共通テストの出題科目に関しては、上記の6科目から最大2科目選択する形になっています。
1科目100点60分で2科目選択
この形式は旧課程の共通テストから変化していません。
数学に比べて「試験形態の変更」にそこまで恐れる心配はありません!!
旧課程の参考書と新課程の参考書を適宜組み合わせて勉強を進めていきましょう!
次に、社会科目に関しても、既に数校の有力大学が発表した「これらの変更を受けて入試範囲に変更を加えるのか」をまとめた表があるので以下に貼っておきます、参考にしてみてください!
https://univ-journal.jp/wp-content/uploads/2022/10/221011_kanb_column_03.png.webp
以上です。
【まとめ】
今回は【新学習指導要領】に伴う、新課程の大学受験について説明させていただきました。
この変更に対応した2025年度入試から、数学や社会等の主要科目にも大幅な変更が加えられ、共通テストの出題形式も大幅に変容を遂げることとなりました。
しかし、高校1年・2年生の皆さんが守るべき「基軸となる勉強スタイル」は依然として変化していません!!
「自分の勉強スタイルが確立できない、、」
「新課程の入試についてもっと詳しい情報が欲しい!」
そのように感じた人は、是非一度無料の受験相談にお越し下さい!
武田塾あざみ野校は勉強する皆さんの味方です!!