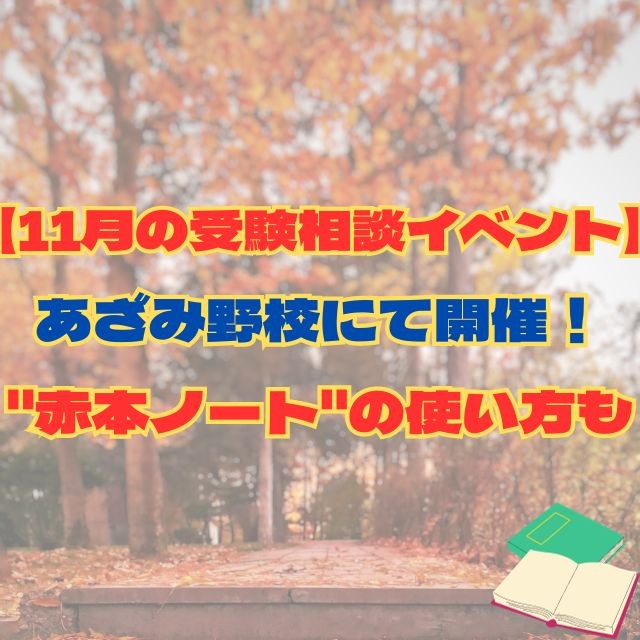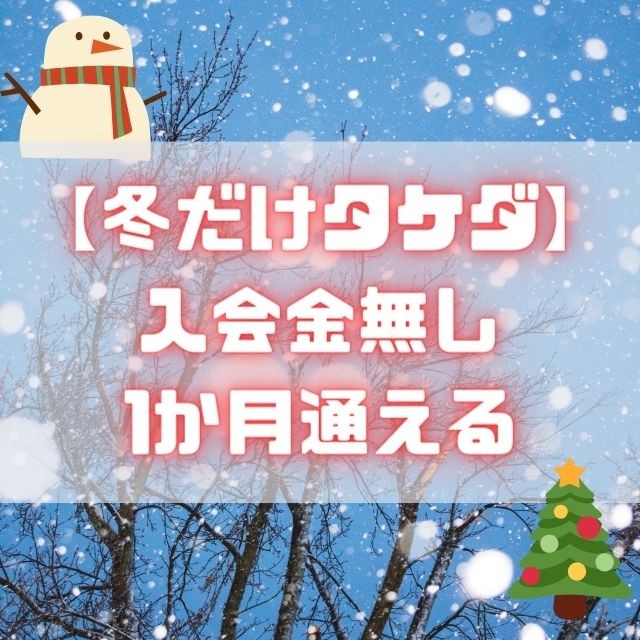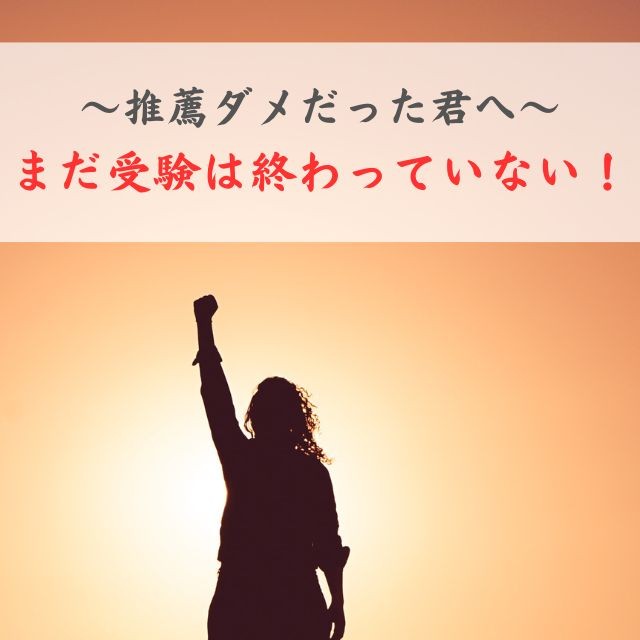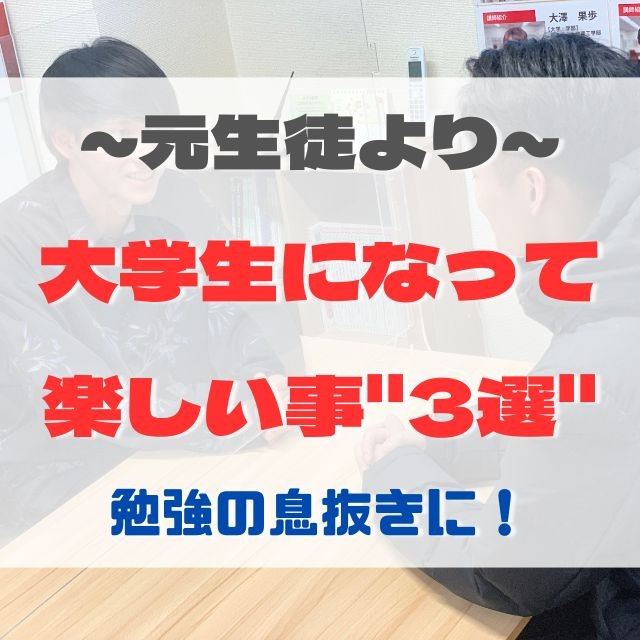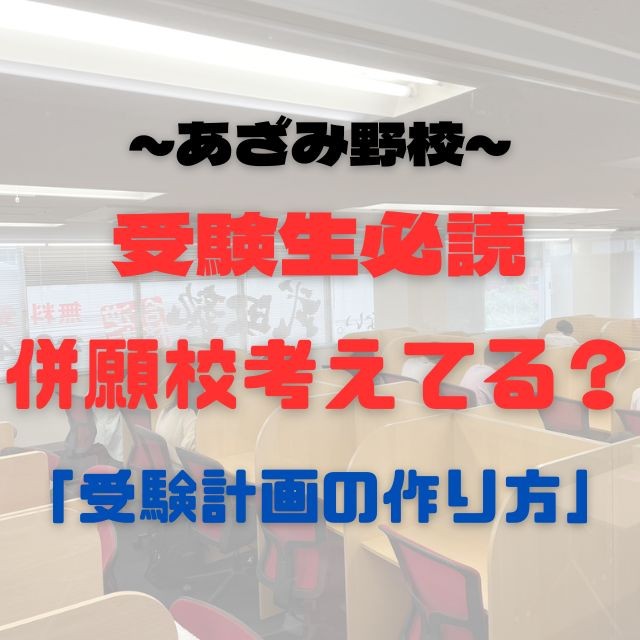
【受験生は必読!】受験計画の作り方!併願校考えてる?
皆さんこんにちは!
武田塾あざみ野校です。
11月に入り、寒くなってきていよいよ受験が近付いてきました!
そこで今回は、受験計画の作り方について話したいと思います!
受験校の決め方!
まずは受験校の決め方から!
①挑戦校
皆さんはこれまで第一志望に向けて努力してきたと思います。
ですが、第一志望に合格できる受験生は10%程度だと言われていて、中学受験、高校受験と同様に、挑戦校、実力相応校、安定校を受験することになります。
多くの人は第一志望校が挑戦校にあたります。
②実力相応校
次に実力相応校ですが、過去問や模試から6,7割は合格できると判断できるレベルの学校(本番に弱いや、新設の学部などで判断しずらいなどは考慮する必要あり)を考えましょう。
③安全校
最後に安定校ですが実はここが重要です。
なぜ重要かと言うと、安定校の判断を見誤ると滑り止めのはずが滑り止まらず最悪全落ちする可能性すらあるからです。
これを防止するためには、この大学以上じゃないと絶対に入学しないなどがある方以外の、今年で必ず合格したい人は大学を侮らずに実力を判断することです。
よくある例は、日大をはじめとした、日東駒専と呼ばれる大学を侮り、対策をきちんとしないまま受験本番を迎えたが、苦手分野が多くて落ちてしまった。
などです。なので皆さんは安定校の判断を見誤らないでください。
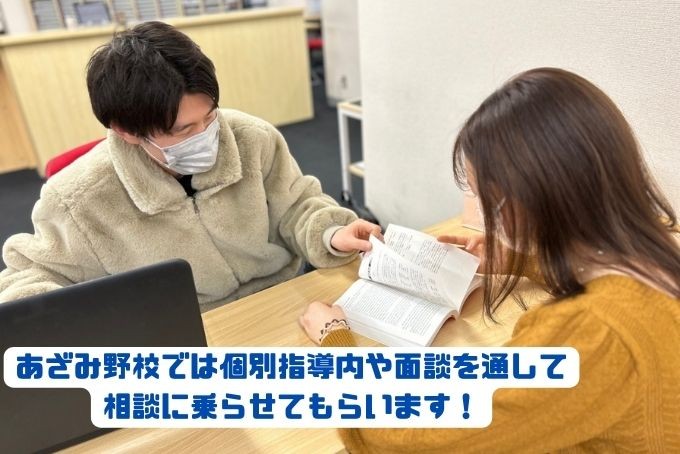
入試方式も重要!
ここで志望校を決める際に気をつける点をお話します。それは入試方式です。
なぜ入試方式が重要かというと、皆さんの最終目標は安定校や実力相応校に合格することではなく、第一志望に合格することだからです。
第一志望の入試方式が個別試験のみの入試形式だったとします。
そこに安定校や実力相応校で共通テストや、小論文が必須になってくると、第一志望の対策時間が減り、合格確立が減ってしまいます。
最終目標を達成するためになるべく入試方式は似ている学校を選びましょう!
国公立志望の生徒向け
今までの話の例外として国公立です。
国公立志望の人は共通テストと二次試験の勉強を両立して頑張っていると思います。
その皆さんは、共通テストが終わった後、各予備校に共通テスト判定を提出することになります。
これにより、全国の全受験生の中での立ち位置、つまり二次試験でどのくらい点数を稼がなきゃならないかを知ることが出来ます。
そこでこれまでの過去問、冠模試などから実際受験する学校を決定しなければならないのです。
受験校を変更する場合も、旧帝大から筑波大などにランクを落とす方法と、同レベル帯の共通テストの比率が低い大学、学部、学科に変更する方法があります。
入試日程について
次は入試日程について話そうと思います!
ここまではレベルや入試方式で受験校の決め方について話してきましたが、ここからは入試日程で実際に受ける学校の絞り込み方についてです。
ご存じの方も多いと思いますが、大学入試は基本的に難易度順に実施されます。
ですので同レベル帯を受けすぎると毎日連続で受験することになります。
体力によって前後するものの4日以上は連続しないように考えましょう。
しかし、日程を分散させまくればいいわけではありません。大学には入学金締切日があります。
そこで安定校の入学金締切日と、実力相応校の合格発表日で入学金締切日の方が早かった場合、払わざるを得ません。
受験校の組み合わせによっては最終的に2,3校に入学金を支払わなければならなくなることがあります。
そうならないために、併願校の候補を決めた後はカレンダーを用いて絞り込むのがいいです。
最終的に挑戦校、実力相応校、安定校それぞれから1~3校程度受けることをオススメします。
最後に併願受験をする時に気をつけた方がいい大学を紹介します。

併願校決める上での注意点
1.共通テスト利用入試
多くの大学に存在する共通テスト利用入試ですが、受けるときには注意が必要です。
なぜかと言うと、共通テスト利用入試ではその人の学力の1~2ランク下の大学しか合格しにくいからです。
共通テスト利用入試は当然共通テストを受験して、出願するだけで合否が出ます。
なので、早慶、国公立の最上位の受験生が滑り止めとして受験することが多く、大学のレベル以上の実力が必要になっています。
なので闇雲に出願せずに、自分の取れる点数と過去のボーダーラインを比べてから出願を決めましょう。
2.上智大学
上智大学は早稲田、慶應に続く難易度の高い大学ですが、入試方法が基本的に、共通テスト併用型と、共通テスト利用型、TEAP利用型です。
共通テスト利用型は前述を参考にしていただきたいのですが、残りの2つは特殊な入試形態となります。
まずTEAP利用型ですが、TEAPとは上智大学と英検が開発した英語4技能試験で、TEAPのスコアが入試の点数に換算されます。
11月に行われる今年最後の試験を受けれない場合、入試すら受けれません。
次に共通テスト併用型ですが、こちらは共通テストと個別学力試験の合計点で合否が決まりますが、その個別学力試験が特殊で、経済学部では数学があったり、文学部では学科と関連する内容。
例えば、フランス文だと、「フランス文学、文化、歴史に関するテクストの読解力および思考力、表現力を問う試験」のように第一志望でなければ負担が大きくなる入試方式となるので注意が必要です。
3.早稲田大学と慶応義塾大学
日本の私立大学のツートップの早稲田と慶応ですが、この二つの大学を併願することは危険があります。
この二つの大学の大きな違いは小論文か国語かです。
慶應は多くの学部で小論文の試験を課し、多くの受験生が小論文対策を行ったことはないと思います。
それにもかかわらず、早稲田の日本トップクラスの国語試験の対策も行うとなると、時間が足りず、共倒れなんてことも考えられます。
併願を考えている場合は現状の学力と、合格まで必要な勉強を考えて決めましょう。
4.芝浦工業大学
最後は理系大学です。
芝浦工業大学と言えば、四工大と呼ばれる大学群のうちの一つで、四工大はMARCHよりレベルが低いなどなめられがちですが、芝浦工大は四工大の中でも頭一つ抜けていて、MARCHに匹敵するほどレベルが高いです。
中にはMARCHを蹴ってまで、芝浦工大を選ぶ人がいるくらいです。
問題のレベルも十分高くなっています。なので四工大を安定校や実力相応校に考えている人は気をつけてください。

最後に
今回は受験計画の作り方について話してきました。
まとめると、まず自分のレベルから挑戦校、実力相応校、安定校の判断をし、受験方式を出来る限り近くする。
最後に受験スケジュールを調整することで受験計画を作ることが出来ます。
「もう少し詳しく計画の立て方について知りたい!」
そういった人は、是非一度"無料受験相談"にお越し下さい。
一緒に自分に合った受験計画を考えましょう!
それでは!