
こんにちは!!
武田塾住道校です!!
今回のテーマは「国公立私立入試動向2024」です。
高校生新聞オンラインにて「私立大学志望動向2024」と「国公立志望動向2024」という記事を基に、
入試形式の変化や志願者の増減などに注目しながらも、
武田塾の見解を加えつつ、各大学の動向を解説していきます。
受験生の皆さんにとって参考になるような記事になっていますので、ぜひ目を通してみてください。
本ブログでは前編として私立大学の動向について説明していきます。
早慶上理MARCH産近甲龍の一般方式が「狙い目」

まず記事のタイトルが「私立大学志望動向2024 早慶上理MARCH産近甲龍の一般方式 非常に狙い目か」となっております。
(リンクも添付)
今の受験生にとって
早慶上理MARCH産近甲龍の一般方式が「狙い目」なのではないかという話があるそうです。
記事では、人口減少・大学志願者数の減少を根拠として挙げております。
また特に武田塾の見解と一致する部分が、「私大志望者の共通テスト離れ」です。
センター試験の時代は、私立大学志望であったとしても、
練習のためにセンター試験を受験するのが当たり前でした。
国公立志望でなくとも、センター利用入試で合格を取れる人は取っておくのが定石でした。
しかし、共通テストになってから難易度が著しく増加し、
共通テスト対策が必須になってきてしまっています。
国公立志望で共通テストの対策を入念に行っている場合ならまだしも、
私立大学志望で共通テストの傾向に合わせて問題を解くのは至難の業と言えます。
私立大学志望が共通テストをうまく利用して滑り止めを取るという時代でもなくなってしまいました。
センター試験は、その難易度は言わずもがな、
傾向として、入念に対策ぜずとも、ある程度の勉強をしていれば点数を取れるテストでした。
しかし共通テストは癖が強い問題が多く、対策をしないと点が取れなくなっています。
私立を目指しながら共通テストで点を取るとなると、
方向性の違う勉強をそれぞれ並行することになり、どちらも中途半端になってしまいかねません。
二兎を追う者は一兎をも得ず状態になってしまいます。
「だったら共通テストはもういいや」という私立大学志望や、
「だったら私立大学はもういいや」という国公立大学志望など、
どちらかに絞るという受験生が増えているのが、最近の傾向です。
実際に、「共通テストの受験者が32年ぶりに50万人を割った」という記述があります。
共通テストを受ける人がそもそも減っているのが現状です。
または、「共通テストを一応受験はするけど、本気で対策はしない」人の割合が増えています。
それほどまでに私立大学志望の間で「共通テスト離れ」が進んでいるのです。
その結果、共通テストが重要である青山学院大学は少し影響を受けています。
志願者数は前年比96%となっており、志願者の減少が見られます。
立教大学は昨年度の志願者数が少なかったので前年比106%となっていますが、
上智・立教・青学のような共通テストを使った入試を盛んにやってる大学は、
今年は少し人気を落としているようです。
明治大学も前年比91%となっていますが、これは去年が多すぎたという見解があります。
入試の仕組みが全然違うので、今年の受験生は明治・中央・法政に流れているようです。
前年比で見ると、早稲田も94%になっていますが、ここから何を得られるという訳ではないみたいです。
産近甲龍が「ねらい目」

昨年度の入試を見たところ、武田塾の見解として、
日東駒専産近甲龍のレベルの大学が、昔と比べてかなり受かりやすくなっています。
各大学で様々な理由があることが考えられますが、
数年前は「日東駒専は意外と落ちる」と叫ばれていた時代に比べて、
日東駒専産近甲龍のレベルの大学は、かなり入りやすくなっている印象です。
その理由の一つとして、受験の早期化が挙げられます。
日東駒専・産近甲龍でも、推薦で前半で合格を決めてしまうことが多く、
その結果、一般入試の競争率が下がっているようです。
今もなめてかかったら落ちることがありますが、
対策をしていれば、全然滑り止めにならない時代ではなくなっているようです。
例えば東洋大学や日本大学商学部などが英検二級で8割扱いという4技能の換算方式を実施しており、
英検2級を取ってくれていれば、後は国語と社会さえ勉強していれば大丈夫になっています。
このようにして、日東駒専産近甲龍は受験をきちんとした人は受かるレベルになってきているとみることができます。
しかし、これは大学自体のレベルが下がっているという意味ではなく、
戦略を立ててしっかりと対策をすれば受かりやすい、ということを改めて述べておきます。
MARCHや関関同立も「狙い目」

MARCHや関関同立の一般入試についても、昔よりは易しくなってきています。
繰り返しになりますが、「推薦入試で早めに決めてしまおう」という層が多いことが最近のトレンドです。
指定校推薦で9月に合格を決めてしまう人もいれば、
11月に総合型で合格を決めてしまう人もいます。
「とにかく早く入試を決めて安心したい」というのがトレンドのようです。
または、「総合型が穴場らしい」「総合型が有利」という、
様々な受験の情報が広がったことで、総合型に切り替える人が増加し、
その結果、一般入試の受験者が減り、
一般入試の争いが以前ほど厳しくなくなってきています。
以上の理由から、きちんと対策をした人ならば合格を勝ち取りやすくなっているのですね。
後期入試が受かりやすい
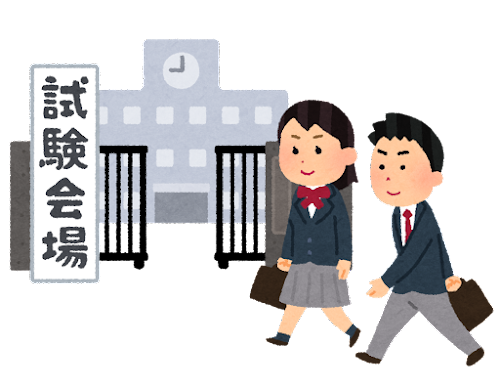
後期入試は今までなら倍率がとても高く、競争が厳しい印象でした。
しかし、今の入試は、入学定員以上にあまり多くの合格者を出せない仕組みになっています。
そのため、後期入試は、辞退者が出て入学定員を下回った分を補填するということで、
受験生にとってだけではなく、大学側も助かる制度になっています。
実際に、昨年度、後期入試にチャレンジしてみたら意外といけたケース
というのが多く見られました。
後期入試にも積極的にチャレンジしていくべきですね。









