皆さん、こんにちは!
南浦和駅徒歩2分、武田塾南浦和校です!

今回は、物理・化学の問題の解き方についてまとめてみました。ぜひ読んで見てください!!
はじめに
新年度になって数か月たち、学校生活や受験勉強にもなれてきたころかなと思います。

しかし、その一方で、勉強しているはずなのに頭がよくなった気がしないと伸び悩んでいる人もいるかもしれません。
また、数学・英語は分かってきたけど、物理・化学とかどう勉強したらいいのかわからないという人もいるかもしれません。
今日はそんな受験生のために、物理・化学の問題の解き方を数学との違いに触れながら、説明していきたいと思います。
多分、生物にもいえるとおもうのですが、僕が生物をきちんと勉強していないため今回は対象から外させてもらっています。
物理・化学と数学はちがう??
理系科目ということで、数学が苦手だから、物理・化学もできないと苦手意識を持っている人もいるかもしれません。
たしかに、無関係とはいえませんが、受験においてこれらの科目はすこし違います。
端的に言ってしまえば、化学→物理→数学の順で、暗記が必要、逆に言えば応用力はあまりいらないです。
僕は生徒に、「数学を料理とするなら、物理・化学はレゴブロックを組み合わせてるようなものだよ」と伝えることがあります。

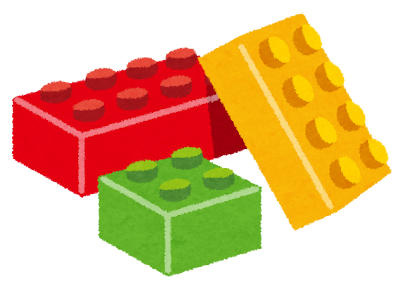
これは、数学は料理のように、どのように切るか、煮るか焼くか揚げるか、など選択肢が多い一方で、物理・化学はどのブロックとどのブロックを組み合わせればいいかを考えるだけで選択肢が数学ほどないということを意味しています。
次では、なぜそのような違いがでるのかを説明したいと思います。
物理・化学の数字・文字・式には意味(単位)がある!!
結論からいうと、物理・化学の数字・文字・式には意味があります。
例えば、1という数字が出てきたとき、物理・化学では、1個なのか1mなのか1kgなのかといった意味(単位)が必ずといっていいほどついてきます。
一方、数学ではただの1でしかないことがほとんどです。
そして、そのような意味を持った数字や文字を組み合わせた式にもちろん意味が含まれています。
そして、物理・化学では右辺と左辺で値だけでなく、意味も一致する必要があります。たとえば、右辺が速度をあらわしているなら左辺も速度を表していなければならないのです。
お手元の教科書や参考書を確認してみれば、右辺と左辺で意味(単位)が同じであることが簡単に確認できると思います。
これは数学ではあまりない感覚ですね。
そして、このような意味のある式を立てようと思うと、数学ほど立てられる式の数が多くないということに気付いてほしいのです!!
その結果、物理・化学の受験で使うような式の形はある程度決まってきます。
レゴの例では、それをレゴのブロックにたとえて、組み合わせるだけだとさきほど述べたのです。
これで物理・化学のほうが数学より暗記が必要なのが、感覚的に理解できてきたと思います。
物理・化学の問題の解き方

ここまで読んで、「いや、組み合わせるって言ったって、どうやって組み合わせればいいんだよ」と思う方もいると思います。
ここでは、それについて書いていきたいと思います。
順番としては、現象の理解→現象を式で表す→計算の3ステップです。
・現象の理解
ここが一番大事といっても過言ではありませんが、ここを見落とす受験生は多いです。
式が難しそうに見えるので、そちらに気を取られがちですが、本当に大事なのはここです。
物体にはどのような力がかかってるのか、これらの物質はどのような反応をしているのか、など問題で起こっていることを理解せずには式を立てることなど不可能です。
図をふんだんに使い、どんなことが起こっているのかを理解することに一回力をいれてみてください
解けない生徒に話を聞いてみると、この段階で詰まっていることが多いです。
問題は、日本語で書かれているので何となく感覚で理解できてる気になってしまっているんです。
しかし、問題を解くためには式にできるように、まずその問題を細かく理解することが大事です。
ここをおろそかにしていると、どれだけ公式を覚えてもどこで使えばいいかわからない、いわゆる初見問題解けない人に陥りがちです。
・現象を式で表す
つぎは、前のステップで理解できた現象を式で表します。
翻訳といってもいいかもしれません。現象の意味を理解したなら、それを式の形で翻訳するのです。
ここで、日ごろ行っている参考書の蓄積を思う存分発揮してください。
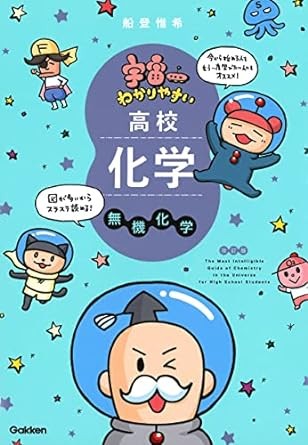
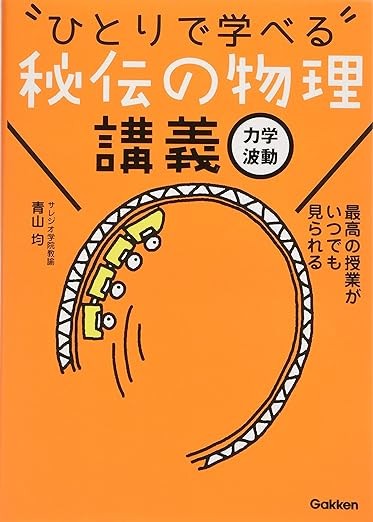
ここは、ほぼ暗記といっても過言ではありません。
速度を表す式、エネルギーを表す式、圧力を表す式、などなど、これらを自力で立式できるなら今すぐ研究者になりましょう。
そうではない人は、参考書で式の形を手になじませて、その現象で立てれる式を立てれれるだけ立ててください。
そのうち、問題を解くために必要な式だけを瞬時に立式できるようになると思います。
・計算
ここまでくればほぼ問題は解けています。
しかし、受験生はこのパートが一番難しいと勘違いしています。
良く式を見てください。
だいたい一次関数、むずかしくても二次関数です。あとは足し算引き算掛け算割り算、いわゆる四則演算です。
ここが難しいなら、たしかに数学の基礎を固め直す必要があります。
しかし、ここまで読んでいる大半の人はそんなことないはずです!
難しくて大事なのは「現象の理解」と「立式」です。
おまけ。
よかったらこちらの動画も参考にしてみてください!
まとめ
いかがだったでしょうか。
もし、これらを理解しても、勉強がはかどらない、
実践してみたけど、毎日継続して勉強ができない、
いつまでにどの参考書を仕上げればいいかわからない、
やっている勉強法が正しいものかわからない、
もっと具体的な勉強法を教えてほしい!
という方は、ぜひ無料受験相談にお越しください!
武田塾では、高1高2含む、すべての受験生に向けた無料受験相談を実施しております!
受験はゴールは一緒ですが、スタート地点はバラバラです。
これはデメリットのように思えるかもしれませんが、これを読んでいるあなたはわかりますね?
今、この瞬間から、スタートしましょう!
武田塾が、あなたの夢を全力でサポートします!!
LINEの友達追加はこちらから!
************************
大学受験の逆転合格専門塾【武田塾南浦和校】
〒336-0018
埼玉県さいたま市南区南本町1-3-4
清水ビル 3階
(JR武蔵野線、京浜東北線南浦和駅西口より徒歩2分!)
TEL:048-872-8444
HP:https://www.takeda.tv/minamiurawa/














