受験生なら一度は手にしたことがあるであろう暗記アイテム「赤シート」。
実は、ちょっとした工夫で勉強効率を大幅にアップさせることができるのをご存じですか?
今回は、赤シートをどう使えば効率的に勉強できるかを解説していきたいと思います。
もう赤シートを日常的に使っているという方も新しい使い方の発見になるかと思いますのでぜひご覧ください。
「赤シート」とは?

赤シートとは、単語帳などの暗記系参考書に付属している半透明の赤いシートです。
オレンジ色の文字の上に赤シートを当てるとその文字が見えなくなるため、これを利用して赤シートを当てた部分の文字を思い出すという使い方をします。
ここでは、赤シートを使うメリットとデメリットを紹介します。
赤シートを使うメリット
メリットとしては、赤シートがあれば効率良く勉強できるようになるという点が挙げられるでしょう。
まず、赤シートを使う暗記の勉強は参考書(単語帳)と赤シートさえあれば可能なため、場所を選ばず勉強できるようになります。
通学中のバスや電車内など、試験までの時間を有効的に使うことができるでしょう。
赤シートを参考書に挟んでおけばすぐに取り出して勉強ができるので、準備に時間をかけず暗記に集中できるのも赤シートを使うメリットと言えます。
赤シートを使うデメリット
非常に便利な赤シートですが、一応デメリットもあります。
それは、赤シートで隠れている部分しか覚えなくなってしまうということです。
赤シートを使うと隠れている部分だけに注目してしまい、文章全体をしっかり読まなくなってしまう恐れがあります。
特に歴史系などの科目では全体の流れを把握したり、文章で説明できる力も必要になってきます。
また、赤シートは小さくいろいろなところに持ち運ぶため無くしやすいというのもデメリットの一つです。
赤シートの効率的な使い方

とても便利な赤シートですが、ちょっと工夫を加えることでもっと効率的な勉強ができるようになります。
赤シートを使いこなすためのコツを、いくつか皆さんにご紹介していきます。
赤シートの効率的な使い方①問題集は赤シートで消えるペンで解こう
書き込むタイプの問題集だと、一度解いてしまうとその後が使いにくくなってしまいますよね。
問題集は一周だけしてもあまり意味がなく、何周もしてようやく身になります。
そこで、問題集を解く際には赤シートで消える色のペンで書き込むようにすると赤シートで隠せるため、その後も答えを見ずに問題集を使えるようになります。
そうすることで、問題集と赤シートを持ち歩くことでどこでも問題を解けるようになり一石二鳥です。
赤シートの効率的な使い方②ペンは水性のオレンジがおすすめ
問題集を解くときは赤ペンでも良いのですが、実はオレンジ色のペンの方がおすすめです。
何故なら、普通の赤ペンだと赤シートを使ってもしっかりと消えてくれずうっすらと透けて見えてしまうことがあるためです。
オレンジ色のペンなら比較的しっかりと消えてくれるため、赤シートと併用するならオレンジ色のペンかピンク色のペンをおすすめします。
また、インクは油性よりも水性の方が良いでしょう。油性だと必要以上に濃くなってしまったり、ノートに跡がついてそれが見えるようになってしまうため注意が必要です。
赤シートの効率的な使い方③赤シートを使う前提でノートを取ろう
普段の授業でノートを取るときには、赤シートで隠すことを前提にすると勉強効率が良くなります。
例えば重要語句をあらかじめオレンジ色のペンで書いたりしておけば、わざわざ後で赤シート用のノートを作る必要が無くなります。
また、そうすることで自然と重要語句に注目するようになるため、授業の理解度もアップするのでおすすめです。
今まであまりノートを見返してこなかったという人もいるかもしれませんが、こうすることでノートが自分専用の参考書として使えるようになるでしょう。
赤シートの効率的な使い方④緑シートとの併用で効率アップ
赤シートと同じように特定の色の文字を消せるアイテムとして緑シートというものもありますよね。
よく赤シートと一緒に売られていますが、この2つをセットで使うことでもっと効率的に勉強できます。
例えば英単語のように単語と意味をセットで覚えたいものに対して有効で、それぞれ片方ずつ隠すことで確実に2つセットで覚える方法がおすすめです。
赤シートの場合はオレンジ・ピンクのペンで消えますが、緑シートは赤色のマーカーで文字を塗ることで文字が見えなくなります。
赤シートを無くさないための工夫とは?
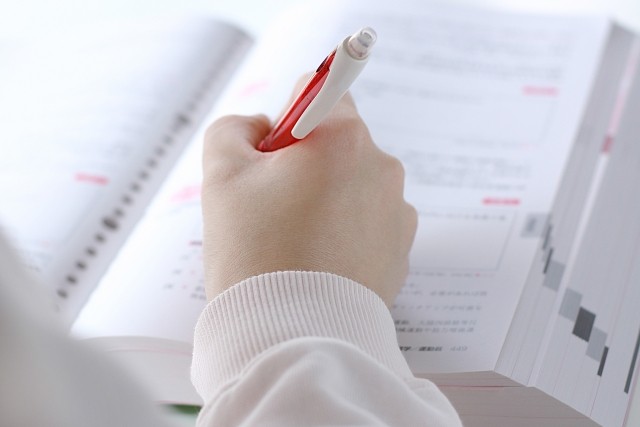
赤シートを使っていると、頻繁に無くしてしまうという経験は無いでしょうか。
特に単語帳に付属しているタイプだと小さいのですぐ無くしてしまい、少し使いづらさを感じてしまいます。
そこで、赤シートを無くさず使うためのポイントを解説したいと思います。
穴を開けてリングファイルに挟む
ルーズリーフのように穴を開けることで、ルーズリーフと一緒にリングファイルに閉じることができるようになります。
これなら絶対に落として無くすようなことはありませんし、ルーズリーフと併用して使いやすいのも魅力です。
1つだけ穴を開けてヒモを通しておくだけでも無くす確率はグッと低くなるのでおすすめです。
また、その際帯状にカットすることで特定の部分だけを隠しやすくなります。
大きいからと言って必ずしも使いやすいというわけでもないので、自分の使いやすい大きさにカットしてみるのも良いかもしれません。
赤いクリアファイルを使う
暗記したいプリントなどを赤いクリアファイルに入れておくという手もあります。
赤いクリアファイルなら赤シートの代わりになるため、プリントやルーズリーフと一緒に、そして無くさずに管理することができます。
中に入れたルーズリーフなどをそのまま隠して暗記に使えるため、使いやすさという点でもおすすめです。
赤い下敷きを使うようにする
ノートを書くときや問題集を解くときに使う下敷きですが、普段から赤くクリアな下敷きを使うことをおすすめします。
赤くクリアな下敷きは赤シートの代用品になりますし、下敷きは基本的に学校や塾に持ち歩くことが多いものなので忘れることもめったにありません。
赤シートと比べて下敷きは厚みもありサイズも大きいため無くすこともないでしょう。
赤シートは参考書や単語帳に差し込んで持ち運ぶことが多く「どの参考書に入れたっけ?」となることもありますが、下敷きならそれがないのも大きなメリットです。
スマホで使える!赤シートアプリ

このとおり非常に便利な赤シートですが、実はスマートフォンでも赤シートが使えます。
ここでは、スマートフォンでの赤シートの使い方をご紹介します。
赤シートアプリとは?
スマートフォンで赤シートアプリをインストールすれば、スマートフォン一つで赤シートを使うことができます。
赤シートアプリは、写真やPDFを取り込むことで実物の赤シートのように単語を隠して暗記することができるアプリです。
スマートフォンに写真やPDFを取り込むので、重い参考書や単語帳を持ち歩かなくても勉強しやすいのが大きなメリットと言えるでしょう。
また、アプリによっては取り込んだ教材にマーカーを引いたり単語を隠す機能があるなど非常に便利です。
赤シートアプリなら少しの隙間時間でも勉強が可能
参考書と赤シートでも通学中・通塾中の勉強は可能ですが、赤シートアプリならより細かい隙間時間も利用することができます。
例えばお風呂やトイレの間、電車待ちの時間、待ち合わせの待ち時間など、参考書を取り出しづらい時間や場所でも赤シートアプリなら暗記に使用することができます。
高校生・受験生は忙しいためこういった隙間時間も有効に活用することが大切です。
スマホは基本的にいつでも手元にあることが多いため、ぜひ暗記や勉強に活用しましょう。
自分に最適な赤シートアプリを探そう
赤シートアプリにはさまざまな種類があり、アプリによっては赤シート以外の機能があることもあります。
例えば取り込んだ参考書のPDFデータや写真から自動で問題文を作ってくれたり、単語帳を作ってくれるという機能です。
こういった機能はスマートフォンやタブレットでの勉強をすることが多くアプリで勉強を完結したい人にはとても便利なものでしょう。
逆に赤シート機能だけのシンプルなアプリのほうが使いやすいという人もいると思いますので、自分に最適なアプリを探してみてください。
赤シートの使い方まとめ
受験勉強では定番の暗記アイテムである赤シートですが、使い方をちょっと工夫するだけで更に勉強効率アップを狙えます。
例えば問題集をオレンジ色のペンで解いたり授業中のノートをオレンジペンを使いながら取ったりすれば、そのまま赤シートで暗記に使うことができます。
他には、赤シート自体に穴を開けてリングファイルに挟んでおけば無くしてしまうこともありません。
既に赤シートを使っている方も多いかと思いますが、ぜひ今回紹介した使い方を取り入れて、赤シートをより効果的に活用してみてください。









